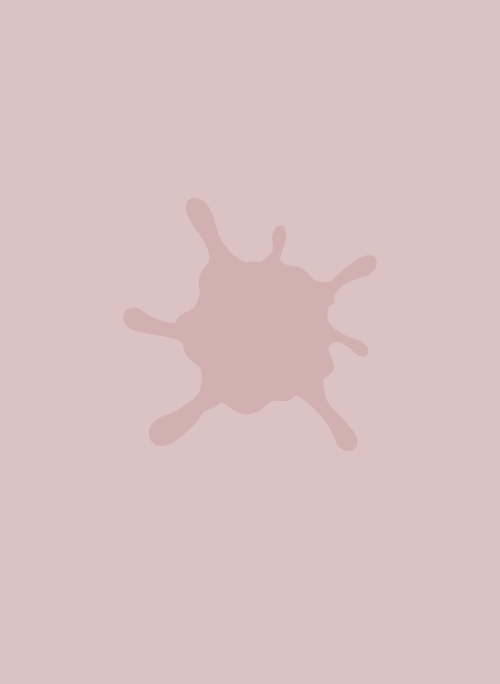「あなたは誰なの?」
「高宮だ」
高宮。真一や由紀と同じ苗字だというのが第一印象だった。
「もしかして高宮真一さんのお父さん?」
高宮は二、三度頷くと、投げやりな口調で言葉を発した。
「そうだ。それよりこちらに質問させてくれないか?」
わたしは高宮の冷たい口調に空気の重さを感じていた。
「君のお父さんの名前は? この辺りに住んでいる人か?」
周りの人はわたしのお父さんに察しがついていたようだが、彼は本当に知らないのかそんなことを聞いてきた。まさかこの人がわたしのお父さんなのだろうか。そう考えれば、お母さんが写真を見て泣いていたのも納得がいった。
お父さんという存在を渇望するかのように、そんな考えにたどり着いていた。
だが、彼を見ると、そんな淡い期待も直ぐに消え去った。
彼はわたしを睨み付けていた。まるでこの世で最も憎いものを見つめるように。わたしはその視線に思わず身を震わせた。
わたしは唇を噛み締める。なぜこの人はここまでわたしを憎らしげに見るのだろうか。その場の空気が重く、首のあたりを締め付けられているような息苦しさを感じていた。
「知りません」
「知らないって」
高宮の言葉が途中で遮られた。彼はわたしの後方に視線を投げかけた。
「高宮だ」
高宮。真一や由紀と同じ苗字だというのが第一印象だった。
「もしかして高宮真一さんのお父さん?」
高宮は二、三度頷くと、投げやりな口調で言葉を発した。
「そうだ。それよりこちらに質問させてくれないか?」
わたしは高宮の冷たい口調に空気の重さを感じていた。
「君のお父さんの名前は? この辺りに住んでいる人か?」
周りの人はわたしのお父さんに察しがついていたようだが、彼は本当に知らないのかそんなことを聞いてきた。まさかこの人がわたしのお父さんなのだろうか。そう考えれば、お母さんが写真を見て泣いていたのも納得がいった。
お父さんという存在を渇望するかのように、そんな考えにたどり着いていた。
だが、彼を見ると、そんな淡い期待も直ぐに消え去った。
彼はわたしを睨み付けていた。まるでこの世で最も憎いものを見つめるように。わたしはその視線に思わず身を震わせた。
わたしは唇を噛み締める。なぜこの人はここまでわたしを憎らしげに見るのだろうか。その場の空気が重く、首のあたりを締め付けられているような息苦しさを感じていた。
「知りません」
「知らないって」
高宮の言葉が途中で遮られた。彼はわたしの後方に視線を投げかけた。