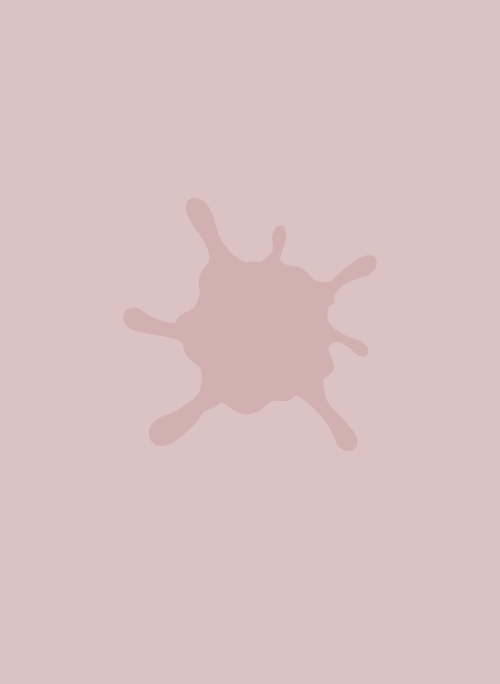真一はわたしが思っていたよりも早く三島さんを呼んでいたのかもしれない。慌てて帰ったのはそろそろ三島さんが来る頃だと察知したからだろうか。
「箒を探していたの」
「墓の合間をフラフラ歩くから何かとり憑いているのかと思った」
三島さんはからかうような笑みを浮かべていた。
わたしは三島さんが菊の花を持っているのに気付いた。わたしがその花を指差すと、三島さんは苦笑いを浮かべていた。
「真一が花を買ってきてくれって言われた。母さんに何がいいかって聞いたら、桔梗にしておけって言われたけど、結局季節外れだからと置いてなかったんだ。それを言ったら残念そうにしていたよ。何で桔梗なんだろうな」
「お母さんの好きな花なの」
三島さんは納得したように苦笑いを浮かべた。
「箒はあいつに取りに行ってもらえば良かったのに。あいつの家の墓もここにあるから、知っているはずだよ」
「用事があるからって先に帰った」
流石に真一に三島さんと仲良くと言われたことまでは言えない。三島さんは溜め息を吐くと、わたしの肩を叩いた。
「じゃ、ついでに置き場所教えるからついてこいよ」
三島さんはそう言い残すと歩き出し、そのまま少し先にある角を曲がってしまった。わたしの視界から彼の姿が確認できなくなった。
わたしは慌ててその後を追うことにした。彼の姿は角を曲がった先にあった。
そこに箒やちりとりなどお墓掃除に必要な道具が一式置いてあるようだ。
複数の人が訪ねてきても大丈夫なようにか、バケツも箒も複数常備してあった。
それを手にお墓に戻ろうとしたとき、三島さんが眉根を寄せた。
「柄杓がないな」
「そういえば」
「いつもはここに置いてあるんだけどね。俺、聞いてくるから待っていて」
三島さんはそう言い残すと、お寺の本堂のほうに歩いていった。
わたしはその場で三島さんを待つことにした。だが、彼はなかなか戻ってこなかった。
「先に掃除をしていたほうがよかったかな」
そう呟いたとき、足元に長い影が届いていた。
わたしは影に促されるようにして、顔をあげた。
端正な顔立ちにスッと伸びた鼻をした、男性が眉根を寄せてこちらを見つめていた。
わたしもその人の姿を見て、思わず声をあげそうになった。なぜなら、わたしはその人を見たことがあったためだ。
あの頃より歳を取り、しわもあったが、お母さんがずっと前に見て泣いていた家族写真に写っていた男性に間違いなかったのだ。
「君は」
彼は顎に手を当てた。
「藤田千明の娘か」
低い声にわたしは一瞬ドキッとした。この人はお母さんの名前を知っていた。顔見知りでしかない可能性もあるはずなのに、言葉では言い表せない妙な感情がわたしを襲った。
「箒を探していたの」
「墓の合間をフラフラ歩くから何かとり憑いているのかと思った」
三島さんはからかうような笑みを浮かべていた。
わたしは三島さんが菊の花を持っているのに気付いた。わたしがその花を指差すと、三島さんは苦笑いを浮かべていた。
「真一が花を買ってきてくれって言われた。母さんに何がいいかって聞いたら、桔梗にしておけって言われたけど、結局季節外れだからと置いてなかったんだ。それを言ったら残念そうにしていたよ。何で桔梗なんだろうな」
「お母さんの好きな花なの」
三島さんは納得したように苦笑いを浮かべた。
「箒はあいつに取りに行ってもらえば良かったのに。あいつの家の墓もここにあるから、知っているはずだよ」
「用事があるからって先に帰った」
流石に真一に三島さんと仲良くと言われたことまでは言えない。三島さんは溜め息を吐くと、わたしの肩を叩いた。
「じゃ、ついでに置き場所教えるからついてこいよ」
三島さんはそう言い残すと歩き出し、そのまま少し先にある角を曲がってしまった。わたしの視界から彼の姿が確認できなくなった。
わたしは慌ててその後を追うことにした。彼の姿は角を曲がった先にあった。
そこに箒やちりとりなどお墓掃除に必要な道具が一式置いてあるようだ。
複数の人が訪ねてきても大丈夫なようにか、バケツも箒も複数常備してあった。
それを手にお墓に戻ろうとしたとき、三島さんが眉根を寄せた。
「柄杓がないな」
「そういえば」
「いつもはここに置いてあるんだけどね。俺、聞いてくるから待っていて」
三島さんはそう言い残すと、お寺の本堂のほうに歩いていった。
わたしはその場で三島さんを待つことにした。だが、彼はなかなか戻ってこなかった。
「先に掃除をしていたほうがよかったかな」
そう呟いたとき、足元に長い影が届いていた。
わたしは影に促されるようにして、顔をあげた。
端正な顔立ちにスッと伸びた鼻をした、男性が眉根を寄せてこちらを見つめていた。
わたしもその人の姿を見て、思わず声をあげそうになった。なぜなら、わたしはその人を見たことがあったためだ。
あの頃より歳を取り、しわもあったが、お母さんがずっと前に見て泣いていた家族写真に写っていた男性に間違いなかったのだ。
「君は」
彼は顎に手を当てた。
「藤田千明の娘か」
低い声にわたしは一瞬ドキッとした。この人はお母さんの名前を知っていた。顔見知りでしかない可能性もあるはずなのに、言葉では言い表せない妙な感情がわたしを襲った。