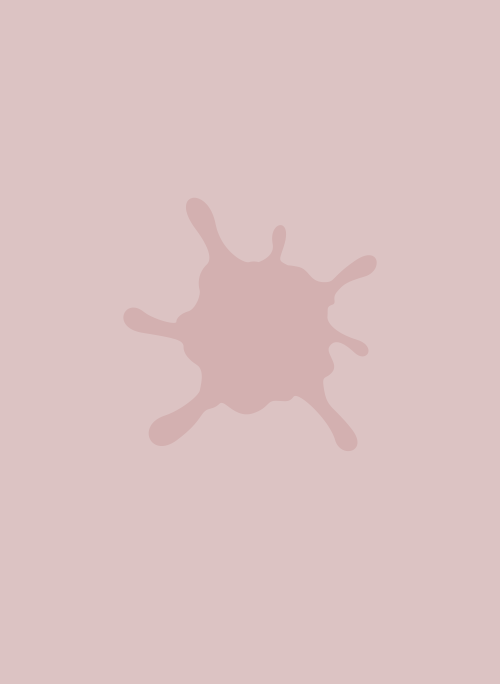わたしはその言葉をやけに新鮮に感じていた。
わたしと千恵子さんはマツさんに案内され、居間に通された。
わたしと千恵子さんをそこに座らせると、マツさんは台所に行き、急須を取り出し、そこに茶葉とお湯を注いでいた。
マツはテーブルの上に三人分のお茶を置くと、わたしの向かい側の席に座る。マツさんはわたしをじっと見たまま一言も言葉を発さなかった。
「初めまして。ほのかと言います」
わたしはその沈黙に耐えられなくなり、口を開いた。わたしの声を聞いて、マツさんの瞳が大きく見開かれる。
「やっぱり千明の子だね。声まで似ているよ」
彼女は顔をしわくちゃにして笑っていた。わたしはその笑顔を見ていると、心が自然と温かくなり、目に涙が溢れそうになる。
わたしがほんの少し泣いているのに気付いたのか、彼女は戸惑いを露わにした。
「ほのかちゃん大丈夫かい?」
わたしは名前を呼ばれ、マツさんをみた。
「平気です。おばあさんがいるという実感がなくて、すごく嬉しくて」
その言葉にマツさんは驚いたようだが、その表情が柔らかくなる。
「ほのかちゃんさえ良かったらここで暮らさないかい?」
マツさんの口から聞こえてきた言葉に、わたしは自分の胸が高鳴るのが分かった。
その胸の高鳴りを戒めるために自らの唇を噛んだ。
わたしと千恵子さんはマツさんに案内され、居間に通された。
わたしと千恵子さんをそこに座らせると、マツさんは台所に行き、急須を取り出し、そこに茶葉とお湯を注いでいた。
マツはテーブルの上に三人分のお茶を置くと、わたしの向かい側の席に座る。マツさんはわたしをじっと見たまま一言も言葉を発さなかった。
「初めまして。ほのかと言います」
わたしはその沈黙に耐えられなくなり、口を開いた。わたしの声を聞いて、マツさんの瞳が大きく見開かれる。
「やっぱり千明の子だね。声まで似ているよ」
彼女は顔をしわくちゃにして笑っていた。わたしはその笑顔を見ていると、心が自然と温かくなり、目に涙が溢れそうになる。
わたしがほんの少し泣いているのに気付いたのか、彼女は戸惑いを露わにした。
「ほのかちゃん大丈夫かい?」
わたしは名前を呼ばれ、マツさんをみた。
「平気です。おばあさんがいるという実感がなくて、すごく嬉しくて」
その言葉にマツさんは驚いたようだが、その表情が柔らかくなる。
「ほのかちゃんさえ良かったらここで暮らさないかい?」
マツさんの口から聞こえてきた言葉に、わたしは自分の胸が高鳴るのが分かった。
その胸の高鳴りを戒めるために自らの唇を噛んだ。