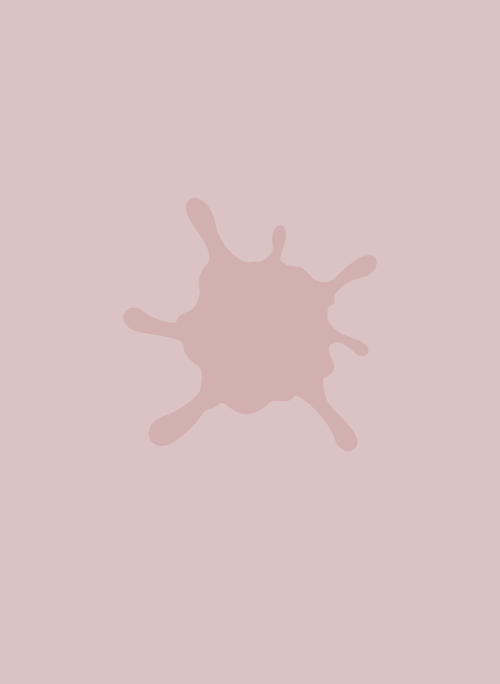少しの沈黙の後、暗い声が耳に届いた。
「なかなか電話ができなくてごめん」
彼はすぐに黙り込んでしまった。
わたしは彼に何も言えず、ただ彼の次の言葉を待っていたのだ。
長い沈黙の後、再び低い声がわたしの耳に届いた。
「話があるんだ。できれば直接会って話がしたい」
「分かった。どこで話をする?」
わたしは気持ちの乱れを気付かれないように、淡々と言葉を綴った。
「花火を見に行った森は?」
「分かった」
わたしは服を着替えると、おばあちゃんに声をかけ家を出た。
家を出る前におばあちゃんが何かを言いかけていたが、何も言わなかった。
表情から何かを悟ったのかもしれない。
家の外に出ると、短く息を吐いた。
辺りはあたたかく、春の気温に満ちはじめていた。
わたしはまっすぐ森に向かう。辺りももう命の源が木々を彩り始めていた。わたしが木々に手を伸ばそうとすると、木陰で佇んでいた鳥が羽を羽ばたかせて飛んでいった。
わたしは自嘲的に笑った。まるで春自体がわたしの目の前から去っていくような気がしていたからだ。
そんな気持ちに分け入るように、背後から土を踏む音が聞こえてきた。振り返ると、三島さんが立っていた。
「なかなか電話ができなくてごめん」
彼はすぐに黙り込んでしまった。
わたしは彼に何も言えず、ただ彼の次の言葉を待っていたのだ。
長い沈黙の後、再び低い声がわたしの耳に届いた。
「話があるんだ。できれば直接会って話がしたい」
「分かった。どこで話をする?」
わたしは気持ちの乱れを気付かれないように、淡々と言葉を綴った。
「花火を見に行った森は?」
「分かった」
わたしは服を着替えると、おばあちゃんに声をかけ家を出た。
家を出る前におばあちゃんが何かを言いかけていたが、何も言わなかった。
表情から何かを悟ったのかもしれない。
家の外に出ると、短く息を吐いた。
辺りはあたたかく、春の気温に満ちはじめていた。
わたしはまっすぐ森に向かう。辺りももう命の源が木々を彩り始めていた。わたしが木々に手を伸ばそうとすると、木陰で佇んでいた鳥が羽を羽ばたかせて飛んでいった。
わたしは自嘲的に笑った。まるで春自体がわたしの目の前から去っていくような気がしていたからだ。
そんな気持ちに分け入るように、背後から土を踏む音が聞こえてきた。振り返ると、三島さんが立っていた。