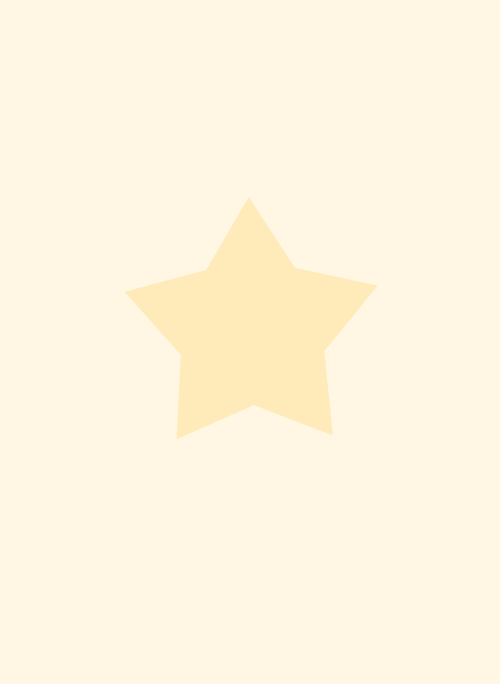私のことを疑っているようだ。
でも、私は何もミスはしていない……はず。
叫び声をあげたときだって、執事さんは私ではなく希夏ちゃんのものだと勘違いしていたし…。
多分、大丈夫………だよね?
「………まあ、いいでしょう」
質問に答えることのできなかった私に呆れたのか、執事さんはそれ以上喋らなかった。
「…………」
「…………」
無言が続き、重い空気が流れる。
食堂までの道のりって、こんなに長かったっけ?と思う。
実際には食堂に行くのに一分もかからないところだが、私は何十分もかかっているように感じられた。
執事さんが食堂の扉を開くと同時に、私は驚いた。
なんと、俊秀も希夏ちゃんのように、まるで感情を持たない家畜のようにひたすら肉を貪っているのだ。
「がうっ、がう、がう、が、がっっ、がうがう、あう」
「がうっ、がうがうっ、がう、がっがう、がうあうがう、あっ」
「俊秀…どうして………」
でも、私は何もミスはしていない……はず。
叫び声をあげたときだって、執事さんは私ではなく希夏ちゃんのものだと勘違いしていたし…。
多分、大丈夫………だよね?
「………まあ、いいでしょう」
質問に答えることのできなかった私に呆れたのか、執事さんはそれ以上喋らなかった。
「…………」
「…………」
無言が続き、重い空気が流れる。
食堂までの道のりって、こんなに長かったっけ?と思う。
実際には食堂に行くのに一分もかからないところだが、私は何十分もかかっているように感じられた。
執事さんが食堂の扉を開くと同時に、私は驚いた。
なんと、俊秀も希夏ちゃんのように、まるで感情を持たない家畜のようにひたすら肉を貪っているのだ。
「がうっ、がう、がう、が、がっっ、がうがう、あう」
「がうっ、がうがうっ、がう、がっがう、がうあうがう、あっ」
「俊秀…どうして………」