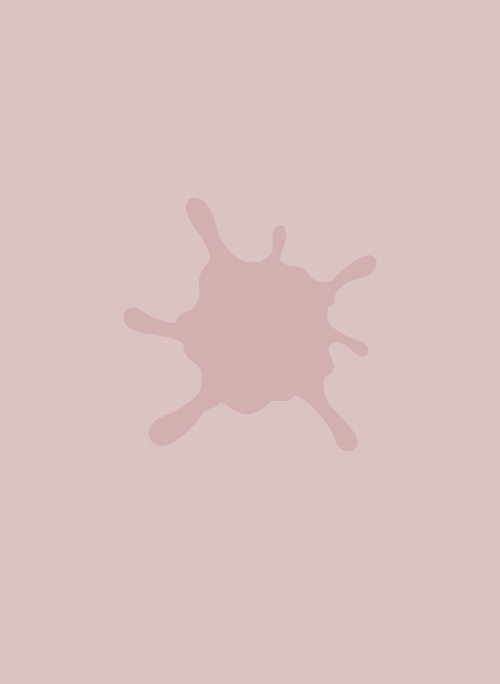「すぐに帰って来るさ。だから少しの間だけ、ここにいれば良い」
もうハルの両親は帰って来ない。
事故でぐちゃぐちゃに潰れて、今は墓の下で眠っている。
彼女には、絶対伝えれない。
だからこれで良い、……これで良いんだ。
ハルは少し表情を和らげ、ペコリと頭を下げた。
「では、少しの間お世話になります」
「ああ。……今日はもう遅いし、休んだらどうだ?明日はお前は仕事が休みだと聞いたが」
「えっ! そうなんですか? 」
もちろん、これも嘘だ。
本当ならば彼女はもう、仕事を退職している。
「明日、お休みかぁ……。なにしよう……。ずっとこの家にいても、貴方に悪いですし……」
俺は思い切って、長年の願いを口にする。
「……なら、明日1日は……キッチンに立って、料理を作ってくれないか」
「え、料理ですか? 」
彼女はキョトンとしながら首を傾げた。
料理はいつも俺が担当している。
だから俺は……、どこかに旅行になんて行かなくても良い。
夜の営みも出来たらしたいが、無理強いはしない。
ただ普通の、新婚生活で彼女が担う筈だった、手料理が食べたいのだ。
ハルはにっこりと笑う。
「はい。別に良いですよ。そんなに上等な物は作れませんが……」
もうハルの両親は帰って来ない。
事故でぐちゃぐちゃに潰れて、今は墓の下で眠っている。
彼女には、絶対伝えれない。
だからこれで良い、……これで良いんだ。
ハルは少し表情を和らげ、ペコリと頭を下げた。
「では、少しの間お世話になります」
「ああ。……今日はもう遅いし、休んだらどうだ?明日はお前は仕事が休みだと聞いたが」
「えっ! そうなんですか? 」
もちろん、これも嘘だ。
本当ならば彼女はもう、仕事を退職している。
「明日、お休みかぁ……。なにしよう……。ずっとこの家にいても、貴方に悪いですし……」
俺は思い切って、長年の願いを口にする。
「……なら、明日1日は……キッチンに立って、料理を作ってくれないか」
「え、料理ですか? 」
彼女はキョトンとしながら首を傾げた。
料理はいつも俺が担当している。
だから俺は……、どこかに旅行になんて行かなくても良い。
夜の営みも出来たらしたいが、無理強いはしない。
ただ普通の、新婚生活で彼女が担う筈だった、手料理が食べたいのだ。
ハルはにっこりと笑う。
「はい。別に良いですよ。そんなに上等な物は作れませんが……」