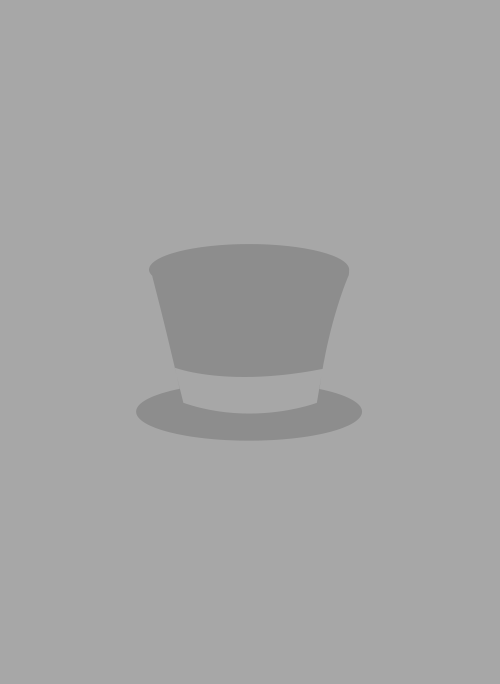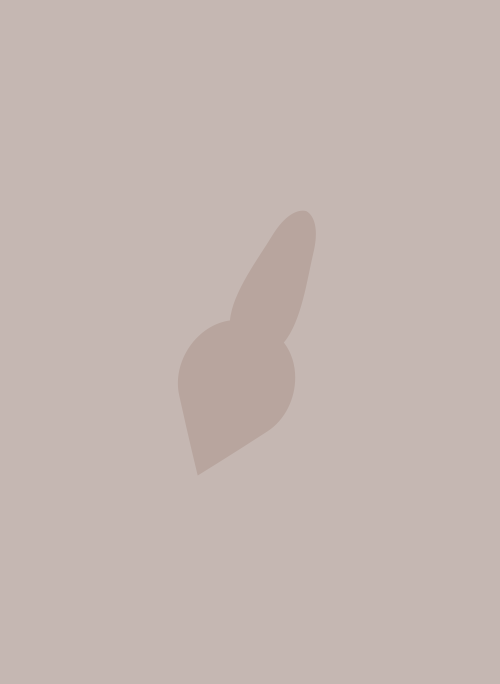「だから何?いつもライブ見に来てるから助けてやったってわけ?ファンサービスのつもり?」
「は?なにそれ?どんなサービスだよ?!」
おっと、つい癖でツッコミを入れてしまった。
そんな私に登はキツい口調で言葉を投げつけてきた。
「なんでアンタみたいな人がメンバーなんかに入れて貰えたんだろうね?どっちか一人、誑し込んだわけ?あ、もしかして二人ともとか?」
「な……」
可愛い顔して最低なこと言ってきやがる!
青く晴れ上がった空とは正反対に、私の心の中では雷雲がうなり始めた。かつてない怒りがフツフツと込み上げてきて。
ヤバい、爆発寸前!
「ふざけないで!なんなのそれ?!私が?あの二人を誑し込んだ?!馬鹿じゃないの!?あの人たちが私なんかにコロッとなるかっつーの!!」
私は登の顔に自分の顔を近づけて、怒鳴り続ける。
「私は、あの二人とバンドがやりたかったの!ただそれだけ!それを彼らはわかってくれたから、メンバーにしてくれたの!」
一気に喋りすぎて、ハァハァと息をしてる私を見て、目の前の登が堪えきれないって感じで噴き出した。
「ぶっ!!あはははっ!……っははは!」
突然お腹を抱え爆笑し始めた登を、私はポカンと見つめ、突っ立っていた。
「え、何?今のどこか笑えるポイント、あったか?」