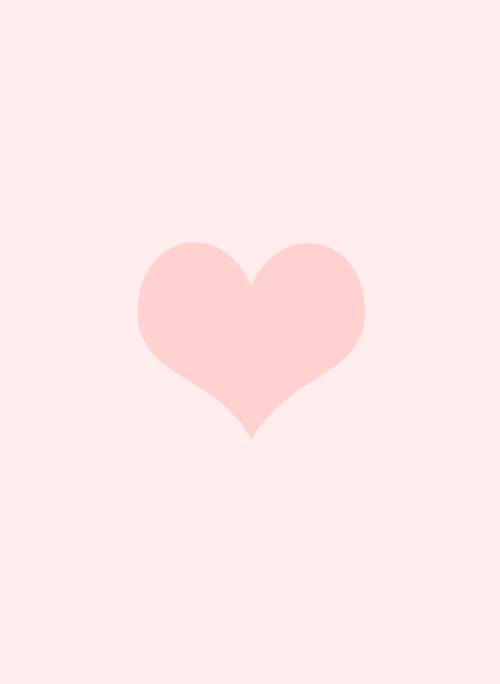ストローベイルハウスは、軸組みした後で、藁をブロック状に固め積み上げていき、土壁を塗る工法と言って良いだろう。
この2種類については、どっちにするか悩んだ。
問題は、材料の調達!
考えて考え抜いた結果、アースハウスでもストローベイルハウスでも大量の粘土が必要だが、どこから調達できるか。
昔、田んぼだったところがそのままになっている場所の土は粘土になっているので、そこの土を貰う方法はないか。
ストローベイルハウスのストローは、稲とか藁、萱、ススキなどが大量にあり、ブロック状に束ねることができれば良いのだ。
色々調べたが、ストローベイルハウスという藁の家を造るのにワークショップという考え方で協力者を募ることが大黒柱の考えと合っていると思った。
田舎であれば米とか藁とか材木とかはその辺に余っているものなのだろうが、都会では買わなければならない。
田舎だとその辺にあるものを材料として使用し、移動もそんなにせず、建築も機械を使わずに、皆の力を結集して人力でつくり、エネルギー消費を抑える建築の考え方にも共感が持てた。
都会では田舎に比較してエネルギー消費は相当大きくなり、材料を海外から調達する場合が特に多くなる。
そんなことを都会人に考えさせるためにも、ストローベイルハウスで物置小屋を作ろうと思って会員を説得しようと試みたが、女性会員が多かったためか、賛同を得られそうもなかった。
ただ、女性建築家集団のボランティア団体や他のボランティア団体と連携して企画したり、市長にも要請したり準備をしてしまった。
でも、お婆さんのことで時間がとられ、ボランティア活動への時間が取れなくなったら、続けられるのだろうかと不安になる。
この2種類については、どっちにするか悩んだ。
問題は、材料の調達!
考えて考え抜いた結果、アースハウスでもストローベイルハウスでも大量の粘土が必要だが、どこから調達できるか。
昔、田んぼだったところがそのままになっている場所の土は粘土になっているので、そこの土を貰う方法はないか。
ストローベイルハウスのストローは、稲とか藁、萱、ススキなどが大量にあり、ブロック状に束ねることができれば良いのだ。
色々調べたが、ストローベイルハウスという藁の家を造るのにワークショップという考え方で協力者を募ることが大黒柱の考えと合っていると思った。
田舎であれば米とか藁とか材木とかはその辺に余っているものなのだろうが、都会では買わなければならない。
田舎だとその辺にあるものを材料として使用し、移動もそんなにせず、建築も機械を使わずに、皆の力を結集して人力でつくり、エネルギー消費を抑える建築の考え方にも共感が持てた。
都会では田舎に比較してエネルギー消費は相当大きくなり、材料を海外から調達する場合が特に多くなる。
そんなことを都会人に考えさせるためにも、ストローベイルハウスで物置小屋を作ろうと思って会員を説得しようと試みたが、女性会員が多かったためか、賛同を得られそうもなかった。
ただ、女性建築家集団のボランティア団体や他のボランティア団体と連携して企画したり、市長にも要請したり準備をしてしまった。
でも、お婆さんのことで時間がとられ、ボランティア活動への時間が取れなくなったら、続けられるのだろうかと不安になる。