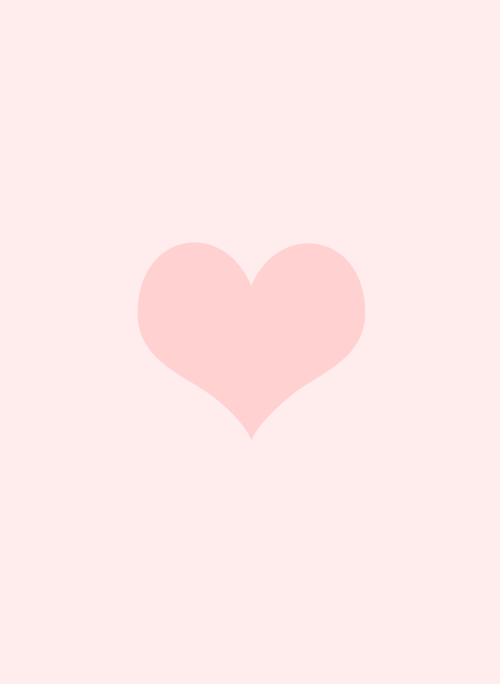パーツのヒット率が一定で、入荷量も出荷量も同月あるいは先週同等で、バックログの数字が増加するのは、戦力不足が起こっているので、技術者が大量に休んでいるか、やめた人が発生し、残業で戦力のリカバリーができないほどダメージを受けている場合が多い。
だから、休む人が多い場合や、やめる人が多い作業環境では、セル方式にするのは危険だ。
一人の技術者が最初から最後まで責任を持って対応するセル方式は、一定の高い技術スキルを持っていることが要求される。
採用時にスキルがあればコストも高くなるので、スキルに拘らないで採用するとその後の教育プログラムが必要になるし、育たないと生産性も上がらない。
その間はバックログが減少しないことになるので、すべてセル方式に変更するのは間違いだったのではないか?
工程で管理する方式も残すべきだったと思う。
今からでも、つくる必要がある。
不安定な部分もあるが、区切りとしてみると、第1到達目標に掲げた返却3日90%以上は目標達成!
さらに、すべての業務に全員が精通すれば営業利益でプラスに!
と、思っていたら…。
*
Output社の方針が顧客満足度重視に変わった!
第2リペアの顧客満足度調査で重視されている項目は、修理時間の短縮と再修理の撲滅である。
オンサイトのように技術者がお客様に訪問して修理する場合は、対面して行うので顧客満足度のベース部分は良いと評価される方に高くなりますが、第2リペアでは対面はしないため、それだけで10%程度はベースとして下がります。
その幅を10%から5%に少なく済めば、顧客満足度が高く評価されたことになるので、目標をそこに置いている。
大黒柱の会社の目論見は、投資した収益の回収であり、営業利益の次は経常利益を狙えるかと考えているとすれば、この話しは違う世界のお話しとして移ることになるだろう。
だから、休む人が多い場合や、やめる人が多い作業環境では、セル方式にするのは危険だ。
一人の技術者が最初から最後まで責任を持って対応するセル方式は、一定の高い技術スキルを持っていることが要求される。
採用時にスキルがあればコストも高くなるので、スキルに拘らないで採用するとその後の教育プログラムが必要になるし、育たないと生産性も上がらない。
その間はバックログが減少しないことになるので、すべてセル方式に変更するのは間違いだったのではないか?
工程で管理する方式も残すべきだったと思う。
今からでも、つくる必要がある。
不安定な部分もあるが、区切りとしてみると、第1到達目標に掲げた返却3日90%以上は目標達成!
さらに、すべての業務に全員が精通すれば営業利益でプラスに!
と、思っていたら…。
*
Output社の方針が顧客満足度重視に変わった!
第2リペアの顧客満足度調査で重視されている項目は、修理時間の短縮と再修理の撲滅である。
オンサイトのように技術者がお客様に訪問して修理する場合は、対面して行うので顧客満足度のベース部分は良いと評価される方に高くなりますが、第2リペアでは対面はしないため、それだけで10%程度はベースとして下がります。
その幅を10%から5%に少なく済めば、顧客満足度が高く評価されたことになるので、目標をそこに置いている。
大黒柱の会社の目論見は、投資した収益の回収であり、営業利益の次は経常利益を狙えるかと考えているとすれば、この話しは違う世界のお話しとして移ることになるだろう。