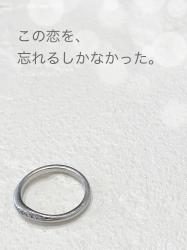「ちょっと見せて。」
「嫌だ…痛い。」
「だから見せてって言ってんじゃん。」
「…ッ!」
なかなか言う通りにしないあたしの顔に、篠田くんの手が触れた。
そこから始まる波紋は一枚の花びらみたいに優しくて、あたしの身体中を一気に駆け巡るーーー…。
避けることなんて、できない。
篠田くんによって開かれたあたしの左目には、入りきらないくらい…篠田くんでいっぱいになっていた。
「う~ん…わかんないなぁ。洗い流した方がいいね。」
「…うん。」
―――と、言った直後だった。
ガラッ
「あなた達、何してるの⁈」
勢いよく開いたドアの向こうには、保健の先生が厳しい表情で立っていた…。
「…失礼しました。」
「…。」
篠田くんは丁寧にあいさつをしていたけど、あたしはそんな気にはなれなかった…。
「嫌だ…痛い。」
「だから見せてって言ってんじゃん。」
「…ッ!」
なかなか言う通りにしないあたしの顔に、篠田くんの手が触れた。
そこから始まる波紋は一枚の花びらみたいに優しくて、あたしの身体中を一気に駆け巡るーーー…。
避けることなんて、できない。
篠田くんによって開かれたあたしの左目には、入りきらないくらい…篠田くんでいっぱいになっていた。
「う~ん…わかんないなぁ。洗い流した方がいいね。」
「…うん。」
―――と、言った直後だった。
ガラッ
「あなた達、何してるの⁈」
勢いよく開いたドアの向こうには、保健の先生が厳しい表情で立っていた…。
「…失礼しました。」
「…。」
篠田くんは丁寧にあいさつをしていたけど、あたしはそんな気にはなれなかった…。