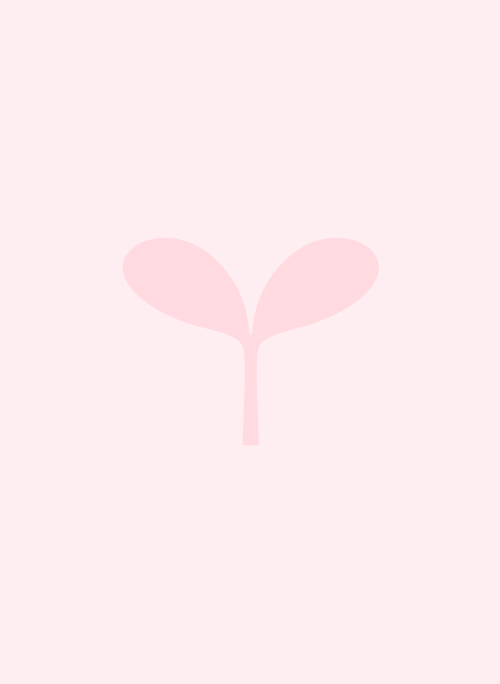「ならば、俺の命を」
共にありたいという願いは、叶えられないが。
それでも、彼女はまだ生きる価値がある。
ダラダラと生きていただけの俺よりも、よほど価値のある生き方ができる。
その見えない瞳の代わりに、彼女の手は驚くほどに全てを美しく見ているのだろう。
その世界に、俺が一時でもあれたこと、大きな誇りではないか。
俺を慕っていると言ってくれた唇は、邪気を知らないもので。
どれだけ俺が……。
『…………』
いつの間にか、目の前に彼は立っていた。
その美しい相貌は、人形のように感情を読み取れない。
『……お前はそれで良いのか』
「………それ以上、望むものはございません」
彼の目をまっすぐに見据えて告げると、その唇が弧を描いた。
『……良かろう』
そして彼は、俺の頭上に手を掲げた。
ゆっくりと千鶴に視線を移せば、彼女の頬を、絶えず涙が伝っていた。
「…………すまない」
その涙を拭って、俺は彼女の瞼に口付けた。
いつか、俺よりも幸せにできる奴に出会え。
そして願わくば。
良い思い出として、時々思い出しておくれ。
千鶴。
愛していた。