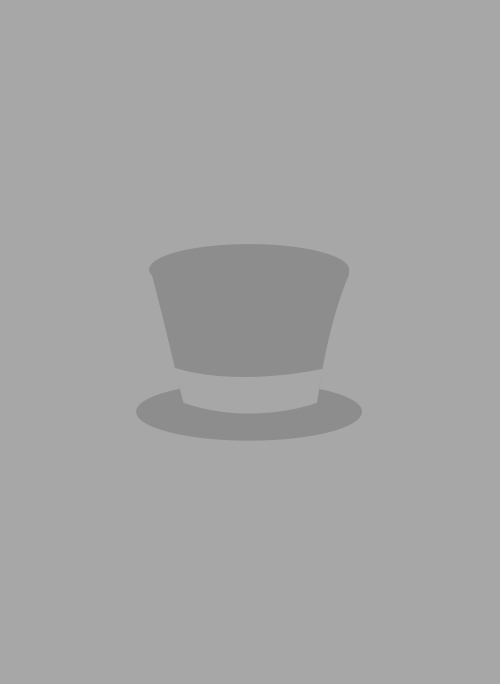「え…心、どうしてここに…」
「それ、わたしの台詞。ふたりこそどうしてここにいるの」
自分が真っ二つに裂けてしまいそうなほど辛いはずなのに、頭は怖いぐらい冷静だ。
「あたしたちは…その、バスケ部の買い出しに…」
「じゃあ手繋ぐことないよね」
ばつが悪そうな顔をし、ふたりは繋いでいた手を離す。
「…噂に聞いていたんだ。ふたりが仲良いってこと」
「だ、誰に聞いたの?」
「そんなことを希和が知る必要はない」
「こ、心……」
「ねぇ、ふたりは付き合っているの」
「……っ」
「ねぇかっちゃん、希和と付き合っているの」
「…心ちゃん……」
「ねぇ、答えてよ。…答えなさいよ」
耳にスマートフォンを当てながら、わたしは聞く。
水樹くんは黙っていた。
「ねえっ!答えなさいよっ!!」
「心っ…落ち着いてっ……」
「希和は知っていたはずだよね!?
わたしがずっと、ずーっとかっちゃんに片思いしていたこと。
希和、応援してあげるって言ってくれたよね!?」
「心っ…!」
「どうして付き合っているの!
わたしの気持ちを知りながら、どうして!」
「落ち着いて心っ…」
「落ち着けるわけないでしょ!
希和、この状態わかっているの!?」
周りのお客さんがわたしたちに注目する。
だけどわたしの暴走は、止まらない。
「希和は、わたしの気持ちを知りながらかっちゃんと付き合った。
ねぇ、この行為が何て言うか希和はわかっているの?」
「……」
「知っていたとしても言ってあげる。これは…」
「やめてっ!」
「裏切りって、言うんだよ」
「心ちゃんっ!」
パンッと、乾いた音が響く。
わたしの頬が、ジンジン痛みを発している。
「やめろ心ちゃん。それ以上言うな」
「……かっちゃん…」
「ああそうだよ。
俺と希和は付き合っている。心ちゃんの思う通りだよ」
「宍戸先輩っ…!」
「希和は何も言わなくて良い」
希和は、かっちゃんに肩を引かれ後ろに下がる。
わたしより背の高いかっちゃんは、わたしを見下ろした。