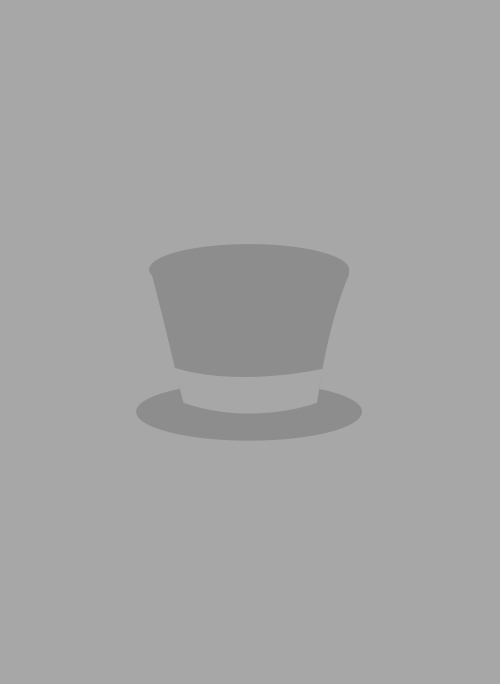色々と話をしているうちに、あっという間に1時間が経った。
つくづく不思議だ。
楽しいと思える時間は一瞬で、大変だと思う時間は長い。
どちらも同じように時間を刻んでいるはずなのに、この差は何だろう。
やっぱり気持ちの問題なのかな。
「1時間経ったから、受け取りに行ってくる」
『じゃ繋げっぱなしにしておいて』
「さっきも思ったんだけどそれで良いの?
ずっと耳に無言のスマホ当てているの大変じゃない?」
『どうして?
話しかけてくれているのに気付かないのは嫌だよ。
それに、ずっと無言のスマホから心ちゃんの声が聞けるのは嬉しいからね』
「…その無自覚に相手を喜ばせること言わない方が良いよ。それじゃ」
何か言っていたけど、わたしは切らないよう気を付けながらポケットに仕舞った。
お店に行き、軽く袋に入れてもらって、再び耳に当てた。
『ねぇどういうこと!?』
「え?…まさかずっと電話口に向かって言っていたの」
『だって気になったんだもん!
心ちゃん、僕が心ちゃんの声が聞けるの嬉しいって言ったの、喜んだの?』
「……」
『僕の無自覚な言葉が、心ちゃんを喜ばせているのなら、僕はずっと言い続けるよ』
「水樹くん…」
『というか無自覚だから、相手を喜ばせる言葉とかわからないや。
いつも思ったことをそのまま言っているから』
「…わたしの声聞くの、嬉しいの?」
『うん、嬉しい。繋がっているから、嬉しい。
僕を知っている人がいるっていうのが嬉しいんだ』
「変なの。
水樹くんを知っているのはそっちでもいるでしょ」
『いるよ。
でも、心ちゃんは特別』
良い加減にしてよ!と怒鳴りたくなる。
勿論、本当に怒っているわけではない。
『僕にとって心ちゃんは特別な存在。
本来出会うことのなかった、奇跡のような存在。
僕はずっとずっと、心ちゃんとの日々を宝物にしていきたい』
「ばっ……馬鹿!」
『ば、馬鹿!?
何で僕馬鹿なんて言われないといけないの!』
「そ、そんなの普通恋人に言うでしょ!
彼女じゃないわたしに言わないでよ!」
『僕にとって今の彼女は心ちゃんだけどなぁ』
「わ、わたしには好きな人が!」
「いるの」
そう言おうとしたわたしは、その場に固まった。
『…心ちゃん?』
「……ッ!」
『心ちゃん?心ちゃーん?どうしたー?』
水樹くんの言葉が一切入ってこない。
まるで、わたしが立つ空間だけ切り取られてしまったよう。
目の前の光景が、テレビを観ているように、他人事に思える。
「……何で…」
向こうも、わたしの存在に気が付き、目を見開いている。
やっと出てきた言葉は、我ながら酷く情けなかった。
「どうしてっ……」
涙が一筋、頬を伝った。
手を繋いでいる希和とかっちゃんは、固まる以外何も思いつかないようだった。