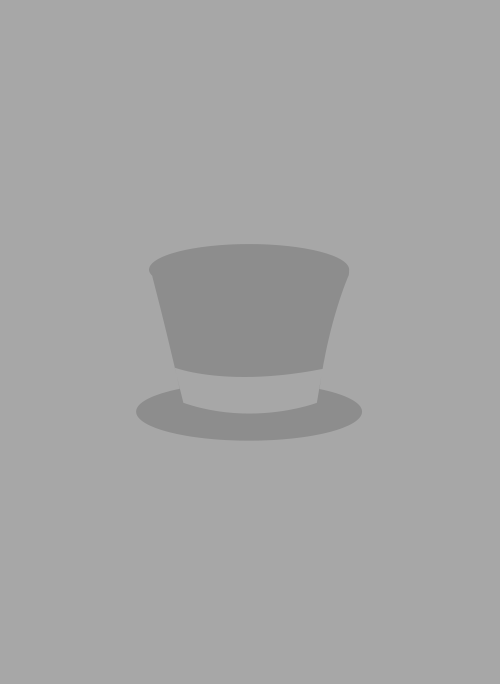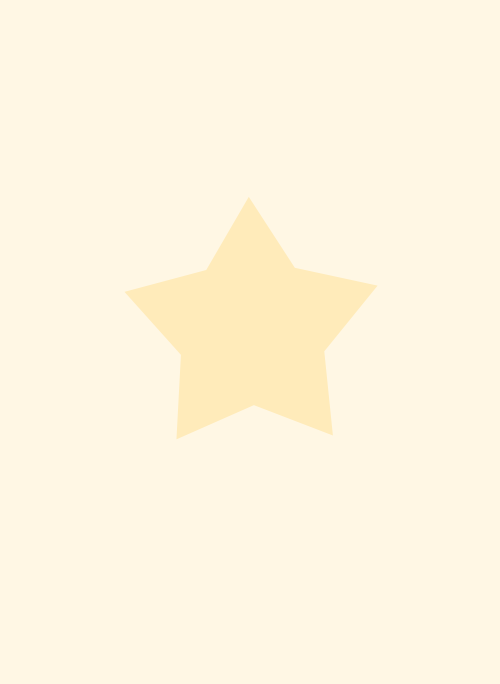だからわたしの人生は、大袈裟かもしれないけどかっちゃん抜きでは語れない。
幼い頃から両親が共働きで、家にいて不安だったわたしの傍にいてくれたかっちゃん。
“頼れる近所のお兄さん”がいつの間にか、“頼れる好きなお兄さん”に変わるのは必然だったと思う。
大好きなかっちゃんと、支えてくれた希和。
そんなふたりが付き合うなんて…嫌だ。
でもまぁ希和はわたしが好きなことを知っているから。
大丈夫だとは、思うけど。
いや、思いたい。
思わせてほしい。
かっちゃんの彼女にならないでね、希和。
『~♪』
「もしもし、水樹くん?」
『やっと出た~!』
「やっと?」
『そうだよ!
心ちゃん何度もかけているのに出ないんだもん。
事故か!?って焦っちゃったじゃん』
「実はクラスメイトの男子に勉強を教えていて。
その間ずっとスマホ鞄の中だったから」
『何何?デート?』
「違うよ!
国語で良い点数取りたいから、トップのわたしに助っ人頼みたいって」
『さ~すが恋する乙女は美人な心ちゃん!
モテモテですなぁ~』
「何それ。ちょっとムカつく」
水樹くんと話していると、自然と笑みが漏れる。
「そういえば水樹くんに教えてもらったの教えたら、その男子わかりやすいって言っていたよ」
『え?あれ教えたの?』
「駄目だった?普通じゃない?」
『いや良いんだけど…恥ずかしいなって思って』
「大丈夫、心配しないで。水樹くんはいつでも恥ずかしいこと言うから」
『えぇっ!?
僕そんな恥ずかしいこと言ってた!?』
「たまにね。
でも半分冗談、さっきのお返し~」
『…最近心ちゃん、敬語抜けてから上手(うわて)になったよね』
「そう?」
『でもそっちの方が堅苦しくなくて僕好み』
「ば、馬鹿っ!」
『あははっ』
「笑うなっ!」
いつものように笑って、他愛のない話をして、水樹くんのアルバイトが始まる時間になったら通話を終える。
真っ暗になった画面を置いた時、わたしの顔には笑みが広がっていた。
水樹くんが、忘れさせてくれた。
希和とかっちゃんのことを。
奥村から聞いた話を、忘れさせてくれた。
「……ありがとう、水樹くん。
ありがとうスマホくん、わたしたちを話させてくれて」
スマホは真っ暗なままだったけど、わたしは嬉しくなった。
「さ、勉強しよう!」