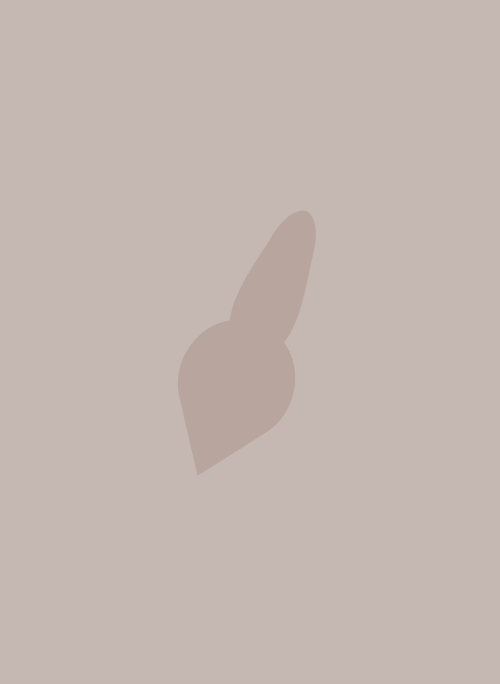蛍と蝉なら、どちらに生まれ変わりたいですか?
先生のその唐突な問いに俺は瞬いた。
蛍と蝉・・・。
俺は縁側で夕涼みをしている先生の横顔をまじまじと見つめ見た。
先生のその見かけの齢は二十代後半から三十代前半と若い。
だが、実際の齢はそんなものではない。
先生は人ではない。
俺はこの人と(人ではないけれど)出逢ったことで多くのことを学び、そして、知った。
俺は自殺を考えていた。
今でもふとした瞬間にそれを考えることがある。
その度に先生は俺の名前を呼び、難しい問いを投げかけてくる。
今はそれを考えてはいなかった。それなのに先生はそんな難しい問いを俺に投げかけて来た。
俺は「そうですね」と呟いて先生の視線の先にあるシャラの木へと目を向けた。
透けるような白い花弁に眩い黄色の雄しべと雌しべが人目を引く可憐な花が夕闇に沈みつつある広い庭でぼんやりと美しく咲いていた。
「叶うなら、俺は花に生まれ変わりたいです」
俺の返答を先生はクスクスと笑った。
先生のその笑いは俺を馬鹿にしたものではなく温かいものだった。
先生はいつだってそうだ。
先生は決して他者を馬鹿にしたりしない。
「すみません。蛍か蝉で聞かれたのに」
「いえ。いい答えを頂きました。ありがとう」
先生はそう言うと僅かに頭を下げ、本当に小さな声で「花」と呟いた。
俺は黙ったまま先生の横に控えて静かな時がじわじわと過ぎ去っていくのを感じていた。
陽が沈んだ。
気温が下がった。
けたたましく鳴いていた蝉が黙り、蜩が静かに鳴きだした。
闇が濃くなり、濃紺の空に月が昇った。
ぼんやりと点滅する儚い光は濃い闇の中を不安気に彷徨いながら飛んでいた。
パタリと小気味よくも悲しい音が静かに聞こえた。
それはシャラの木の花が地に落ちた音だった。
パタリ・・・。パタリ・・・。
「シャラの木の花は一日花です。陽が落ちるとああして落ちてしまう」
先生は憂いを帯びた表情でそう言うと横に置いていた愛用の三味線へと手を伸ばした。
先生は三味線の弦を撥で打たずに爪弾き、その独特の音を楽しむように目を閉じた。
「私は恋を知らない」
先生は苦笑混じりにそう言うとそっと俺を見つめ、僅かに微笑んだ。
何故、この人はこんなにも落ち着きがあり、柔らかいのだろうか?
俺はいつも思う。
先生のようになりたいと・・・。
それは到底、叶わない願いだ。
わかっている。
それでも俺は・・・。
「私は君といることで多くのことを学び、そして、知りました」
「え?」
それはきっと、何かの聞き間違いだ。俺はそう思った。
「私は人として生まれ、人として死にました。けれど、私は生き返ってしまった。・・・いや、化け物に生まれ変わってしまった」
先生はそこまでを言うとクツクツと笑い、短い唄を三味線の音にのせて口ずさんだ。
恋に焦がれて 鳴く蝉よりも 鳴かぬ蛍が 身を焦がす
その言葉の意味を俺はよく知らない。
けれど、先生が何かを思いそれを口にしたことは明白だ。
先生は意味のないことを決して口にしない。
「君にぴったりな唄ですよ」
先生は静かにそう言うと三味線をそっと縁側に置き、裸足のまま庭へと降りて地に落ちたシャラの木の花を一つ拾い上げ、笑った。
「私はいつ、死ねるのでしょうね?」
先生のその言葉に俺は否応なくゾッとさせられた。
先生に出逢っていなければ先生の側にいなければ先生があの時、俺を守ってくれていなければ俺は間違いなく死んでいた。
先生に出逢わなければ・・・俺は死を怖いと思うこともなかったのだろう。
「・・・人は何故、人と関わり生きるのでしょう?」
俺の問いに先生は「そうですね」と呟き、ゆっくりと俺の元へと歩み寄って来てくれた。
「人は人と関わることで己を知り、他を知ります。人は独りでは自分と言うものを認識できない。自分を認識できないと言うことは自分の存在を認識できていないのと同じことだと私は思うのです」
先生の返答に俺は重く頷いた。
自分の存在・・・。
「人は弱い。弱い故に己の存在理由を知りたがる。何故、自分は生まれ、何故、生きているのかと・・・。私は思うのです。その答えを知るには他と関わることでしか知り得ないのではないかと・・・」
先生はそう言うと手の内でシャラの木の花を優しく転がした。
「花のように咲き、蛍のように燃え、蝉のように鳴けたなら・・・」
先生はそこまで言うと口を閉ざし、淡く微笑んだ。
先生のその唐突な問いに俺は瞬いた。
蛍と蝉・・・。
俺は縁側で夕涼みをしている先生の横顔をまじまじと見つめ見た。
先生のその見かけの齢は二十代後半から三十代前半と若い。
だが、実際の齢はそんなものではない。
先生は人ではない。
俺はこの人と(人ではないけれど)出逢ったことで多くのことを学び、そして、知った。
俺は自殺を考えていた。
今でもふとした瞬間にそれを考えることがある。
その度に先生は俺の名前を呼び、難しい問いを投げかけてくる。
今はそれを考えてはいなかった。それなのに先生はそんな難しい問いを俺に投げかけて来た。
俺は「そうですね」と呟いて先生の視線の先にあるシャラの木へと目を向けた。
透けるような白い花弁に眩い黄色の雄しべと雌しべが人目を引く可憐な花が夕闇に沈みつつある広い庭でぼんやりと美しく咲いていた。
「叶うなら、俺は花に生まれ変わりたいです」
俺の返答を先生はクスクスと笑った。
先生のその笑いは俺を馬鹿にしたものではなく温かいものだった。
先生はいつだってそうだ。
先生は決して他者を馬鹿にしたりしない。
「すみません。蛍か蝉で聞かれたのに」
「いえ。いい答えを頂きました。ありがとう」
先生はそう言うと僅かに頭を下げ、本当に小さな声で「花」と呟いた。
俺は黙ったまま先生の横に控えて静かな時がじわじわと過ぎ去っていくのを感じていた。
陽が沈んだ。
気温が下がった。
けたたましく鳴いていた蝉が黙り、蜩が静かに鳴きだした。
闇が濃くなり、濃紺の空に月が昇った。
ぼんやりと点滅する儚い光は濃い闇の中を不安気に彷徨いながら飛んでいた。
パタリと小気味よくも悲しい音が静かに聞こえた。
それはシャラの木の花が地に落ちた音だった。
パタリ・・・。パタリ・・・。
「シャラの木の花は一日花です。陽が落ちるとああして落ちてしまう」
先生は憂いを帯びた表情でそう言うと横に置いていた愛用の三味線へと手を伸ばした。
先生は三味線の弦を撥で打たずに爪弾き、その独特の音を楽しむように目を閉じた。
「私は恋を知らない」
先生は苦笑混じりにそう言うとそっと俺を見つめ、僅かに微笑んだ。
何故、この人はこんなにも落ち着きがあり、柔らかいのだろうか?
俺はいつも思う。
先生のようになりたいと・・・。
それは到底、叶わない願いだ。
わかっている。
それでも俺は・・・。
「私は君といることで多くのことを学び、そして、知りました」
「え?」
それはきっと、何かの聞き間違いだ。俺はそう思った。
「私は人として生まれ、人として死にました。けれど、私は生き返ってしまった。・・・いや、化け物に生まれ変わってしまった」
先生はそこまでを言うとクツクツと笑い、短い唄を三味線の音にのせて口ずさんだ。
恋に焦がれて 鳴く蝉よりも 鳴かぬ蛍が 身を焦がす
その言葉の意味を俺はよく知らない。
けれど、先生が何かを思いそれを口にしたことは明白だ。
先生は意味のないことを決して口にしない。
「君にぴったりな唄ですよ」
先生は静かにそう言うと三味線をそっと縁側に置き、裸足のまま庭へと降りて地に落ちたシャラの木の花を一つ拾い上げ、笑った。
「私はいつ、死ねるのでしょうね?」
先生のその言葉に俺は否応なくゾッとさせられた。
先生に出逢っていなければ先生の側にいなければ先生があの時、俺を守ってくれていなければ俺は間違いなく死んでいた。
先生に出逢わなければ・・・俺は死を怖いと思うこともなかったのだろう。
「・・・人は何故、人と関わり生きるのでしょう?」
俺の問いに先生は「そうですね」と呟き、ゆっくりと俺の元へと歩み寄って来てくれた。
「人は人と関わることで己を知り、他を知ります。人は独りでは自分と言うものを認識できない。自分を認識できないと言うことは自分の存在を認識できていないのと同じことだと私は思うのです」
先生の返答に俺は重く頷いた。
自分の存在・・・。
「人は弱い。弱い故に己の存在理由を知りたがる。何故、自分は生まれ、何故、生きているのかと・・・。私は思うのです。その答えを知るには他と関わることでしか知り得ないのではないかと・・・」
先生はそう言うと手の内でシャラの木の花を優しく転がした。
「花のように咲き、蛍のように燃え、蝉のように鳴けたなら・・・」
先生はそこまで言うと口を閉ざし、淡く微笑んだ。