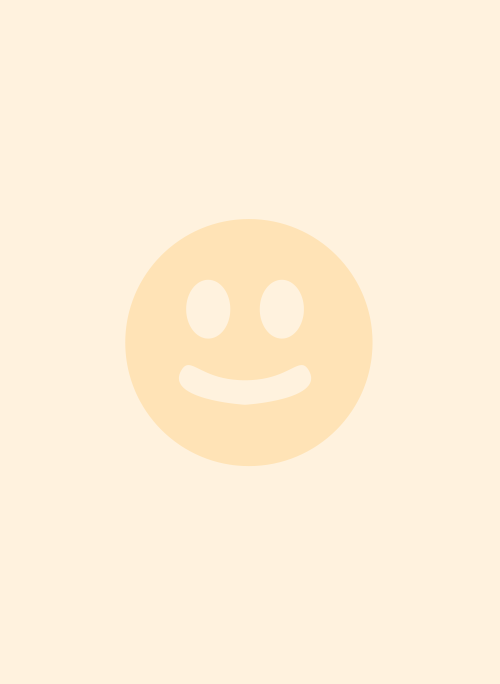「結婚したのが26歳で、男にしちゃ早かったな。大学の同級生と、付き合ってすぐだった。俺は男性営業を育てる研修室から脱出したところで、丁度仕事が面白くなってきた頃だったんだ」
しかも結婚をした。妻は多少体が弱くて、働いてなかった。だから俺が頑張って、たくさん給料を持って帰るんだって張り切ってもいた。
仕事にのめりこんだ。それがとても楽しかった。自分に酔って、一生懸命働くことだけに価値を見出していた。平日もアポを満タンにいれて、分刻みで動いていた。休日だって勿論出勤して、夜遅くまで接待していたんだ。これは全部、妻の為だと言い聞かせて。
私は助手席から平林さんを振り返る。それは紛れもなくハードワーカーだ。
「・・・それで、奥さんは寂しくなった?」
口を挟んでしまった。彼は前を見たままでうんと頷く。
「新婚なのにいつでも俺はいない。疲れると熱を出すから体を気遣ってそんなに外にも出られない。彼女は寂しかったと思うよ。でも自分の為だと張り切る俺を止められなかった。実際のところ、会話をする暇もなかったんだ。・・・そして彼女は――――――」
出て行った。
ある日、家に戻ると彼女は居なかった。暗い家のテーブルに書き置きだけがあった。
俺はしばらく立ちすくんでいたんだ。何が起こったのかが理解出来なくて。
「・・・長い手紙だったんだよ。ずっと自分が考えていたことを、全部書きたかったみたいだった。溜まっていた不安や寂しさ、怒り、全部を出したかったんだろうなあ」
あなたに私は必要ないわ、て書いてあった。あなたは一人でも大丈夫って。