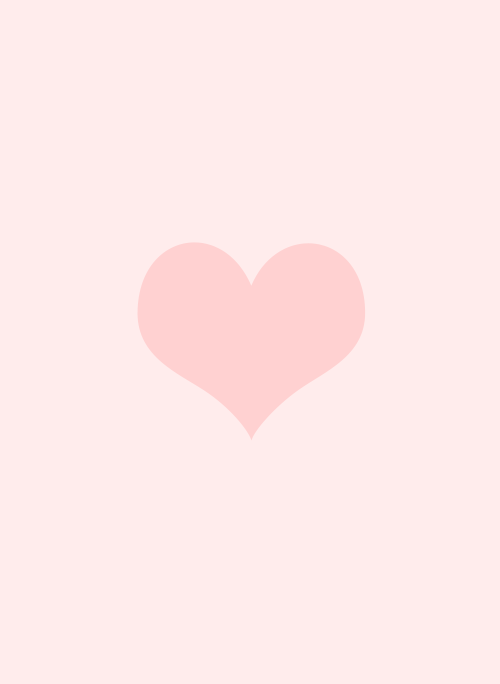弘也のお母さんは「もちろん」と答えてから、そろそろ切ると言って電話を切った。
ツーツーという無機質なその機械音を、しばらくの間聞いていた。
「…、弘也、俺…」
もう一度戦いたかった。
声にならなかった言葉が、涙となって頬を伝っていく。
機械音を止めた。手から携帯が滑り落ち、布団の上で一度はずんだ。
電話のために起こした体を、もう一度布団の中に沈めた。
常識から明日の朝と言ったけれど、本当は今からでも会いに行きたい。
だって、どっちにしろ今からも眠れないだろう。
「…ったく、夜中って…、最後までお前は周りに迷惑かけて、なんで…」
涙が、嗚咽が邪魔をして、言葉が声にならなかった。
何度も何度も嗚咽を繰り返しながら、何度も何度ももういない弘也に問いかけた。
なんで、死んだんだよ。なんで、お前なんだよ。なんで、いなくなるんだよ。
問いかけたところで返事は帰ってこない。
目を閉じると、まぶたの裏に弘也の笑顔が浮かんできて、泣き顔が浮かんできて、そのせいで余計に眠れなかった。