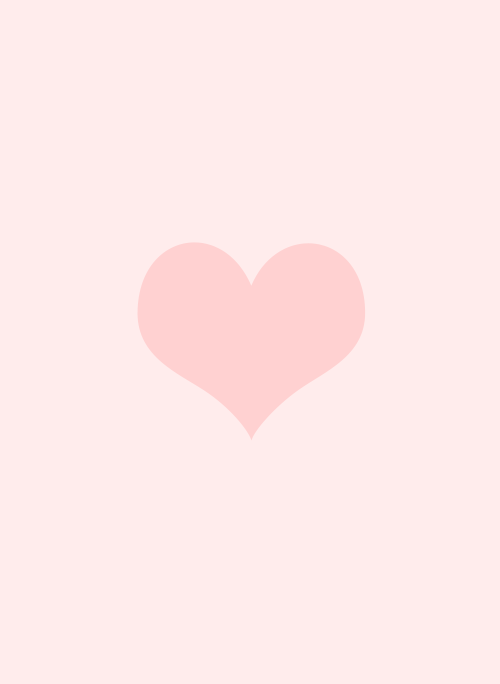その言葉の意味を理解するまでに、そう時間はかからなかった。
17歳になれた俺が羨ましいだなんて、去年の弘也なら考えもしないこと。
それを、いま、このときに考えているなんて、口にするなんて。
「なに、言ってんだよ。お前だってまたあとに17歳になるだろう」
驚いて少しだけ震えた声で、なんとか言葉を口にした。
弘也はそうだなと愛想笑いをしてから、ピタリと笑うのをやめた。
やっぱりやめた、そう呟きながら笑うのをやめた。
「分かってんだよ、俺。体が、もう限界だって言ってるんだ。分かってるんだ」
その期間がどれくらいかは知らずとも、弘也は自分がこの先長くないことを知っていたようだ。
いや、分かっていたようだ。
誰からか聞いたわけではないが、弘也の体が限界だと悲鳴をあげていたのだ。
この先長くないことを、弘也に教えていたんだ。