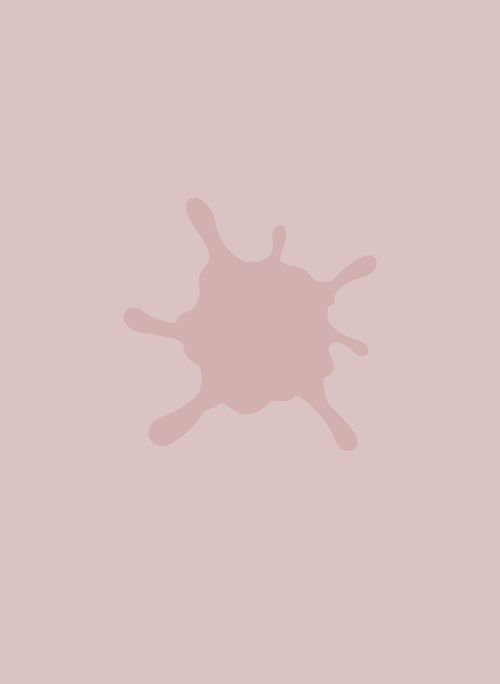駅を降りるとわたしは海への道を急いだ。まるで何かに急き立てられるかのように、駆け出していた。だが、わたしの淡い気持ちは潮風にかき消された。川本さんどころか、人の気配さえなかった。
わたしの視界がじんわりとかすんだ。分かっていたはずなのに、何を期待していたのだろう。
急く思いでわたしは携帯を取りだしていた。そして、彼に電話をかけていた。
だが、呼び出し音がならなかった。
わたしは携帯を手に、その場にうずくまった。
電源が切れたのかもしれない。前向きに考えようとしても、ネガティブな気持ちが一瞬で飲み込んでしまった。
彼はわたしの前からふっと消えてしまうのだろうか。あのときのように。
あのとき。そう。また会えると再会の約束をして、わたしの前から去っていってしまったかのように。
わたしは自嘲的に嗤った。今のわたしは間違いなくやばい人だ。
そもそも彼とそんな約束をしたことさえないのに。
何を考えているのだろう。
そう思っても、目からあふれてくる涙は増える一方だった。
吹き付ける風は強くなり、太陽の位置も徐々に低くなっていた。
わたしの視界がじんわりとかすんだ。分かっていたはずなのに、何を期待していたのだろう。
急く思いでわたしは携帯を取りだしていた。そして、彼に電話をかけていた。
だが、呼び出し音がならなかった。
わたしは携帯を手に、その場にうずくまった。
電源が切れたのかもしれない。前向きに考えようとしても、ネガティブな気持ちが一瞬で飲み込んでしまった。
彼はわたしの前からふっと消えてしまうのだろうか。あのときのように。
あのとき。そう。また会えると再会の約束をして、わたしの前から去っていってしまったかのように。
わたしは自嘲的に嗤った。今のわたしは間違いなくやばい人だ。
そもそも彼とそんな約束をしたことさえないのに。
何を考えているのだろう。
そう思っても、目からあふれてくる涙は増える一方だった。
吹き付ける風は強くなり、太陽の位置も徐々に低くなっていた。