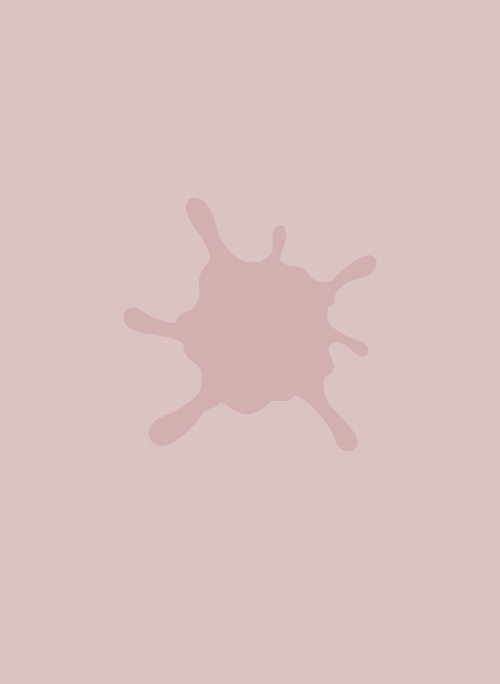「変な言い方してごめんね」
千春は肩をすくめて天井を仰ぐ。彼女の視線が天井から降りてきて、再びわたしの姿をとらえた。
「わたしが生まれてから父親が仕事をしていた記憶がないのよ。職業柄わたしが見なかっただけかもしれないけどね」
「お父さんの仕事は脚本家だよね?」
父親が書いた映画だと言っていたからだ。
彼女は首を横に振る。
「小説家だったの。藤井久明って知っている?」
「知っている。それがお父さんなの?」
千春は頷いた。
結構有名な小説家だったらしいという話を聞いた。らしいというのは図書館などにはたくさん納入されていたが、私の記憶のあるうちにはたいしたヒットも飛ばしていないからだった。新しい作品を書いていないなら納得はできる。ただ、逆をただせばそんなわたしでも名前を知っているレベルの有名な作家なのだ。
「あの映画の脚本家は名前が違うよね。藤亮大って」
「名前、似ているでしょう? 別の筆名だよ。父親が伯父に頼み込んで、脚本を書かせてもらったの。彼女で映画を撮ることは前もって決まっていたし」
「どうして?」
「母親に彼女を演じてほしかったらしいわ。ギャラもいらないからって」
彼女は目を細めて微笑む。頬を赤く染め、どこか嬉しそうに見えた。
「お父さんはそのときから水絵さんのことを好きだったの?」
「母が亡くなった今でも彼女に支配されてしまうくらいにね」