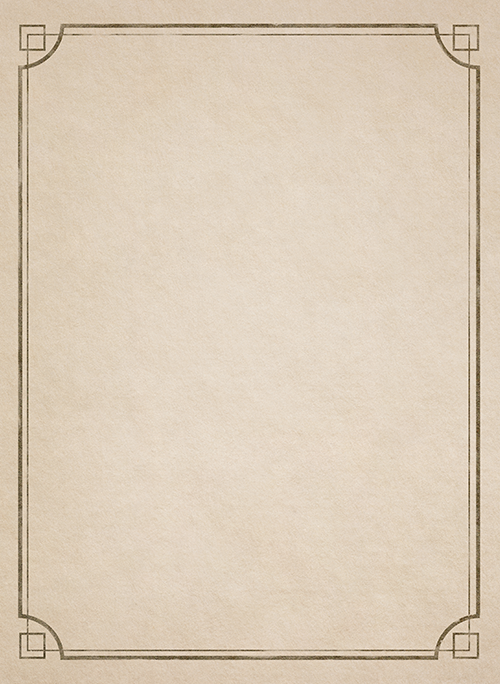「…どうしたって…伝わらない人間っているんですね…」
綺麗事なんて反吐が出る。
良治君は心底幻滅した顔で俯いた。
「…兄貴はもうこの世にいないのに…見守っているだとか…そんなものどうでもいい…そんな…慰め…役に立たない…」
四年間、良治君は一度も少女のお見舞いに行っていない。
それは、なぜか。
そこまで琳子は考えることが出来なかったのだろうか。
無神経な励ましも、押しつけの正義感と綺麗事も相手によっては心を蝕む毒にしかならない。
「…あの日を思い出さない日はないですよ…あの日あの子が兄貴と一緒にいなければ兄貴は死ぬことはなかった…あの子と出会わなければ、兄貴はここにいたんだ…俺は一生あの子を恨むし、許さない。見舞いにも多分いかない。目が覚めてもあの子から聞くのは謝罪の言葉のみだと思ってます…そんな俺に…あんな…バカみたいな綺麗事…」
良治君も、誰かを恨む事で生きていた。
憎しみを育てることでしか心の平穏を保てない程に、恨みが深い。
そんな人間に頑張れなんて言える人間の気がしれなかった。