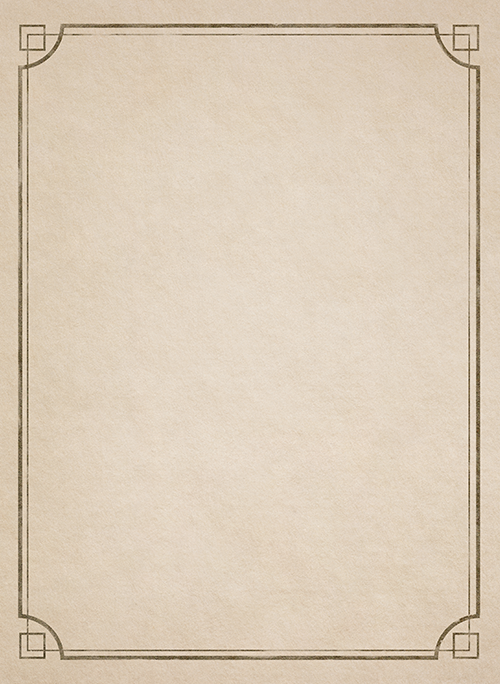「…俺、実はすぐにあの子は目覚めると思っていたんです…なんでかな…」
良治君は彼の名前の刻まれた石を見つめながら、呟く様に零した。
「…兄貴がいなくなって…本当は見舞いとか…俺がいかないといけないのに…麻奈さんに全てまかせっきりにしてるし…多分兄貴がいたら俺怒られるんだろうなとか思ったらほんと情けなくて…」
麻奈は自分の傘を良治くんの為にさし、俯いていた。
「…お見舞いなんて…行ってほしくないよ…」
「…もう四年も経つんですけど…未だに想うんです…兄貴が、生きていたらなぁって…会いたいなって…情けない話本当に良い兄貴だったからたまに無性に会いたくなるんですよね…男のくせにって思うかもしれないですけど…」
「…いるよ。幹斗(かんと)さんはずっと良治くんのそばに!いつもそばで良治君のこと見守ってくれてるよ!だから悲しくても一緒に頑張ろう?」
優しい声色だった、それはここには似つかわしくないくらいに穏やかな声だった。
一層強くなった雨が叩き付けるように降っている。
自分の脳が琳子のこの発言を処理するのに時間がかかっている間に、六つも年下の良治君が笑顔で彼女にお礼を言っていた。
「…琳子…悪いんだけどやっぱり傘…人数分買ってきてくれないかな…このままじゃやっぱりみんな風邪…ひいてしまう…か、ら」
疑問顔の琳子はそれでも素直にわかったと頷きこの場から走り去っていった。
自分の身体がこれ以上濡れるのが嫌だったのかも知れない。