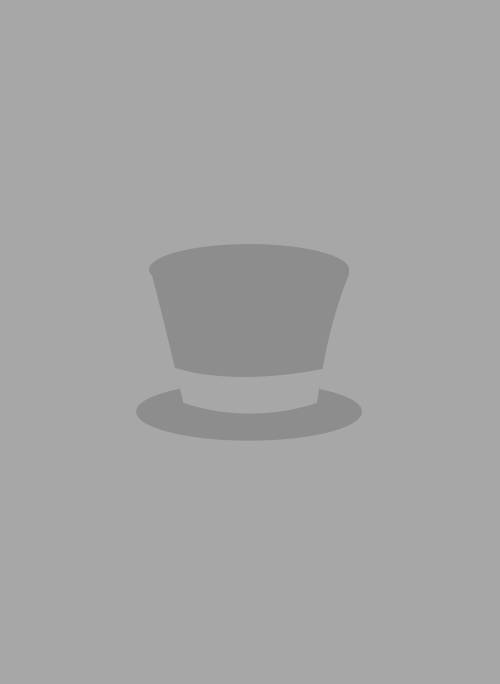「……いただきます」
「召し上がれ」
シエルは小さく両手を合わせ、スプーンを持ち、お粥を口に運んだ。
「美味しい?」
「……すっごく美味しいです。
こんなにも美味しいもの、初めて食べました」
「大げさよ」
わたしにとっては当たり前の食事も。
村出身のシエルにとっては珍しい光景なのかもしれない。
「……美味しいです…すごく……」
「ちょっシエル!?」
わたしはふわふわなスクランブルエッグをすくっていたスプーンを置き、
シエルの隣に驚かせないよう静かに座った。
「シエル、大丈夫?」
「ごめんなさっ……本当に美味しくて…」
美味しさのあまり泣き出したシエル。
わたしは背中をさすりたい気持ちを押さえ込み、シエルの名前を呼んだ。