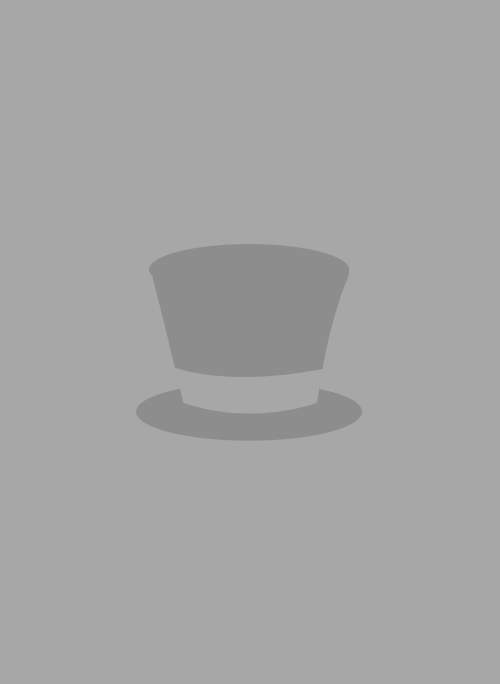国王様と王女様が来るとミーティングで言っていたからか、お屋敷の中は酷くピリピリしていた。
僕もトイレ掃除をしていたが、いつもはひとりでやるのに今日は5人でやっていた。
僕以外の4人が完璧主義者だったため、
僕がふらふらの状態でも構わず綺麗にし、トイレはあっという間に綺麗になった。
他にも窓拭きや床拭きなど様々な仕事をこなした。
使用人の体調なんて、誰も気に留める人などいなかった。
そして数時間後。
国王様と王女様が見え、応接室に通したとメイド長から聞いた。
下っ端の僕は黙って厨房に他の人たちと一緒に立っていた。
あの日からソンジュさんは僕に嫌がらせをすることをやめた。
ただ、たまに酷く冷たい目をして睨み付けてくる。
……自分は助けない上嫌がらせをしてきたというのに、助けてを言うから突き放したら睨み付けるなんて。
むちゃくちゃすぎないか?
「……ごめんなさい…少しお手洗いに行ってきます」
聞いているか聞いていないか定かではないが、隣の執事に言い、僕はトイレへ行く。
行って早々、個室に駆け込みそのまま吐き出す。
食べていないのに吐き気だけは一人前にあるらしい。
どうやら僕も、少しは人間みたいだ。
「…………っ」
廊下を歩いていると、眩暈がして壁に寄り掛かる。
さっきから眩暈が強くなり熱が上がったように思える。
立っていられなくてしゃがみ込みたいけど、誰かに見つかったら何されるかわからない。
誰も通っていない静かな廊下で、儀式を思い出して僕は震えていた。
もう、いつも震えているような状態になっていた。
「……セレーネ」
「っ!」
目を閉じ眩暈に耐えていると、名前を呼ばれる。
急いで顔を上げると、立っていたのはメイド長。
手に湯気の立つ紅茶がはいったティーカップとお皿が乗ったお盆を持っている。
「暇よね」
「え?」
「あたくし、面倒だからあなたに頼むわ」
「……どういう意味ですか」
「これを持って、応接室に行きなさい。
そして紅茶を、国王と王女に渡してきなさい」
「ぼ、僕が……ですか」
「ええ。逆らったらクビよ」
クビ。
待っているのは両親の暴力。
僕は反射的に頷いて、お盆を受け取った。
思ったより、重たい。
「応接室の場所はわかるわよね、行きなさい」
メイド長は軽い足取りで廊下を歩いていく。
僕の手に乗ったお盆の上にあるティーカップが、カタカタと揺れる。
僕の手がカタカタ震えている証拠だ。
僕は強く目を瞑り、開けると歩き出す。
あの幸せな人たちの前に行くのは気が引けるし怖いけど。
クビになんて、なりたくなかった。