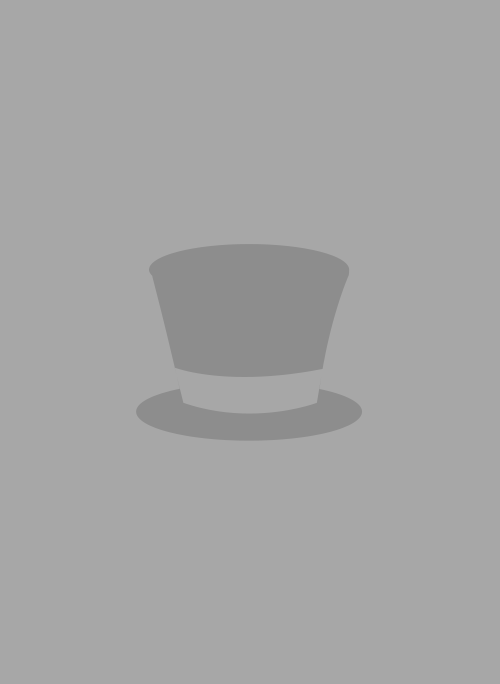ソンジュさんが殴られているのを、離れた所から傍観していると。
殴られていた輪から抜けたソンジュさんが、僕のもとへ傷だらけでやってきた。
「お願いします!助けてください!」
「っ」
「お願いします!!」
涙を溢れさせながら僕に助けを求めるソンジュさん。
周りの使用人たちは、僕がどういう行動を取るのか黙って見守っていた。
その時、何だか心がスッと冷えた気がした。
気が付けば、胸倉を掴み、自分の方へソンジュさんを引き寄せていた。
「俺がヤられている時に助けねぇで笑ったのに、
自分がその立場になったら助けてなんて、
虫が良すぎねぇ?」
知っていた。
ソンジュさんが笑いながら僕に鉄パイプを振り落したことも、
ソンジュさんが説明を勝手にカットして僕が怒られるのを笑って見ていたことも、
僕へ皆に隠れて個別に暴力を振るっていたことも。
僕は全部、全部、知っている。
僕は鉄パイプをグッと握り、振り落とした。
一層、ソンジュさんの悲鳴が地下室に轟いた。
僕は痛みに顔を歪めるソンジュさんの襟元を掴み、ズルズルと地下室の中央へ引っ張っていく。
パッと手を離すと、ソンジュさんは冷たい床に倒れ込んだ。
「続き、するのであればしてください」
「「「…………」」」」
僕は中央から離れる。
すると、待っていた使用人たちがソンジュさんを殴り始める。
僕はそれを、冷えた気持ちで見ていた。
……馬鹿みたい。
あれぐらいで痛い痛い苦しいってのた打ち回っちゃって。
あれ以上、僕は受けてきているっていうのに。
しかも、ずっと僕を笑って助けてくれなかったくせに、助けて?
笑いさえも漏れないよ、本当に。
そんなことを冷静に思いながら、手はガタガタ震えていた。
僕は、この手で、ソンジュさんを殴った。
殴ることなんてデキナイと言いながら、殴った。
両親と、一生同じにはなるまいと誓っていた両親と同じ過ちを犯した。
「……怖いっ…」
ソンジュさんを殴る音と悲鳴だけが響く空間で。
僕は鉄パイプを握りながらずっとずっと、震えていた。
助けて。
お願い、助けて。
誰か、誰か誰か誰か、助けて。