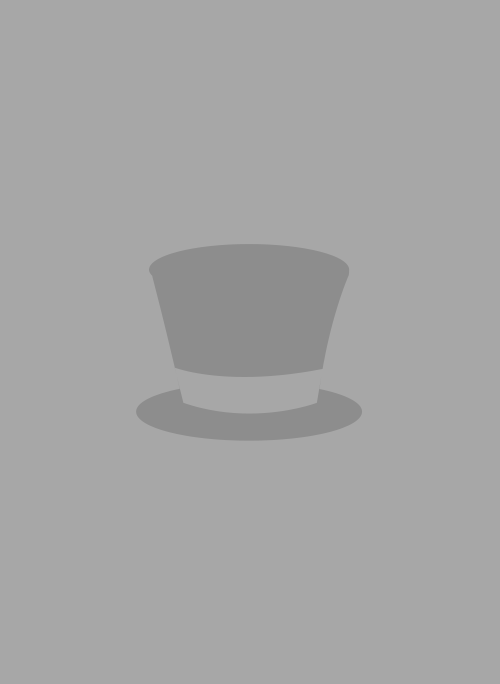「ねぇシエル……あのね」
『コンコンコンッ』
わたしの声に被さる、ノックの音。
わたしはシエルの手を握ったまま、「どうぞ」と声をかけた。
入ってきたのは、シェフだった。
「失礼致します。
シーくん!無事だったか!!」
「……シェフさん!」
シエルは立とうとして、顔をしかめてふらついた。
ポスンッとベッドに戻ったシエルを見て、シェフは驚いたように目を見開いていた。
「シーくん大丈夫か?」
「っ……大丈夫です。
ちょっと、足挫いちゃったみたいで…。
数週間すれば普通に歩けるようになるので」
「そうか…。
本当にごめんねシーくん。
一緒にあの時帰っていれば良かったね」
「いえ、シェフさんのせいじゃないです」
シエルは首の辺りを空いている手で何度もさする。
シェフは、入り口に向かって「入れ」と声をかけた。
入ってきたのは、ふたりのメイド。
手にはお盆を持っていた。