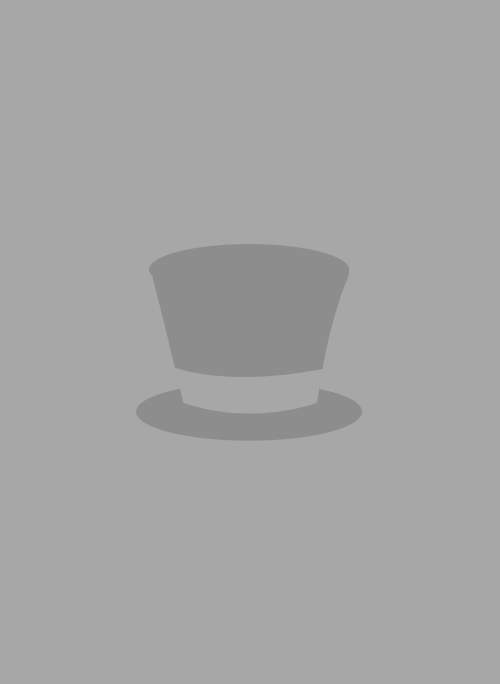「にしてもあ゛ー!
何と言うことを俺はしてしまったんだ!
すまんシエル!!」
「気にしないで……謝らないで良いんだよアンス」
僕の震えがようやく治まり、アンスは僕を離してベッドに座らせてくれた。
のは良いんだけど。
それからずっとアンスは、僕を抱きしめたことについて謝罪をしている。
「つーかシエル、頼み事があるんだ」
「何?」
「さっきのこと、俺の彼女に言わないでくれ」
「……は?彼女?」
「俺彼女いるんだよ。
他校だから知らねぇのも無理はねぇんだけど。
会っても絶対に、俺がシエルを抱きしめたこと言わないでくれ。
あれはアメリカの文化と似たようなもので、
シエルが酷く震えているから放っておけなくて……って!
放っておけないとか、マジですごい発言じゃん俺!!」
「アンス。
僕が安心したのは事実だから、言わないよ」
「……俺は同性愛者ではない。
恋愛は自由だと思っているが、俺は違う」
「わかってるよ。
彼女さんのこと大事にしてあげてね」
僕はクスクスと笑い、ふと切り出した。
「僕さ……中心街出身じゃないんだよね」