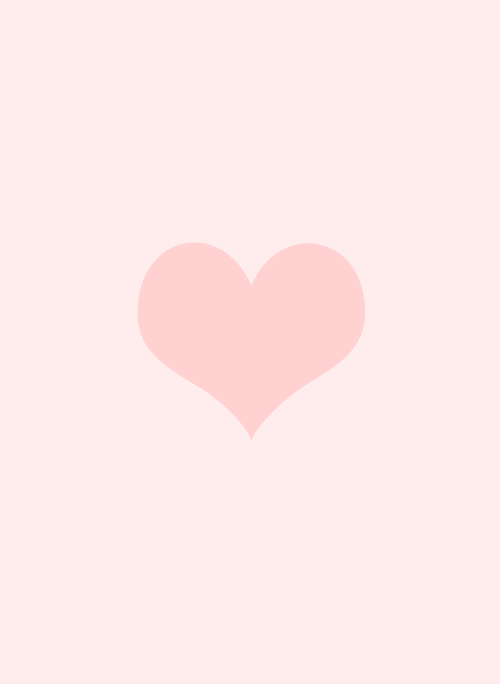以前にも彼女と似たようなことを言った女はいた。
だけどその時の俺にはそれで何かが響くことはなく、ましてや彼女には初めから感じたものでさえ感じたことも無かった。
そのことが理由づけるように、それはすぐに打算のもとに取り繕われたものだとわかって、結局は俺をブランドだとでも思っているのか、隣に立つ俺で周囲の視線を集めることに執着していた。
他の女達もそう。
自分の男(カレシ)だとでも言いたげなアピールを周囲に見せつけて、その頻繁なまでの態度にも俺は正直うんざりしていた。
だけどそこはギブ&テイクで、俺はその見返りに感情の無い行いを繰り返していた。
お互いの欲望を満たすだけの割り切った付き合い。
でも、今隣にいる彼女はいっさいそうしたことは何も求めてる風には見えなかった。
俺から近づいたとはいえ、俺の機嫌をうかがってくることもない。
だから俺はそんな彼女の前では肩の力を抜くことが出来ていたんだと思う。
俺をとりまく環境。
それをものともしない彼女の姿勢が、俺が感じていた甘い痛みに募る想いを増幅させて支配する。
だけど、それと同じだけ増していく不安に心が苦しくなった。
塗り替えればいいと簡単に考えていたけど、それはほどなくして怖さに変わった。
自分のしてきたことに“後悔”という言葉が重くのし掛かり、決して消すことの出来ない過去に足元を掬われる。
そのポジション(恋人)を求め、願えば願うほど踏み出せない。
それでも彼女なら受け止めてくれるかもしれない。
どうしようもなかった俺を認め、許してくるかもしれない。
その身勝手な考えに全てを打ち明けてしまいたくなる。
だけどもし…そのことを知った彼女が俺から離れていくことになったらとまた考えて、その可能性が0(ゼロ)じゃないことに、さらに心が押しつぶされそうになった。
そしてどんどん彼女にのめり込んでいく自分と、臆病な自分にがんじがらめになる。
"失いたくない"
『先輩?』
俺が黙ったままなことに彼女が不思議そうにして、少し近づいた顔が斜めに俺をのぞき込んできた。
だけどその時の俺にはそれで何かが響くことはなく、ましてや彼女には初めから感じたものでさえ感じたことも無かった。
そのことが理由づけるように、それはすぐに打算のもとに取り繕われたものだとわかって、結局は俺をブランドだとでも思っているのか、隣に立つ俺で周囲の視線を集めることに執着していた。
他の女達もそう。
自分の男(カレシ)だとでも言いたげなアピールを周囲に見せつけて、その頻繁なまでの態度にも俺は正直うんざりしていた。
だけどそこはギブ&テイクで、俺はその見返りに感情の無い行いを繰り返していた。
お互いの欲望を満たすだけの割り切った付き合い。
でも、今隣にいる彼女はいっさいそうしたことは何も求めてる風には見えなかった。
俺から近づいたとはいえ、俺の機嫌をうかがってくることもない。
だから俺はそんな彼女の前では肩の力を抜くことが出来ていたんだと思う。
俺をとりまく環境。
それをものともしない彼女の姿勢が、俺が感じていた甘い痛みに募る想いを増幅させて支配する。
だけど、それと同じだけ増していく不安に心が苦しくなった。
塗り替えればいいと簡単に考えていたけど、それはほどなくして怖さに変わった。
自分のしてきたことに“後悔”という言葉が重くのし掛かり、決して消すことの出来ない過去に足元を掬われる。
そのポジション(恋人)を求め、願えば願うほど踏み出せない。
それでも彼女なら受け止めてくれるかもしれない。
どうしようもなかった俺を認め、許してくるかもしれない。
その身勝手な考えに全てを打ち明けてしまいたくなる。
だけどもし…そのことを知った彼女が俺から離れていくことになったらとまた考えて、その可能性が0(ゼロ)じゃないことに、さらに心が押しつぶされそうになった。
そしてどんどん彼女にのめり込んでいく自分と、臆病な自分にがんじがらめになる。
"失いたくない"
『先輩?』
俺が黙ったままなことに彼女が不思議そうにして、少し近づいた顔が斜めに俺をのぞき込んできた。