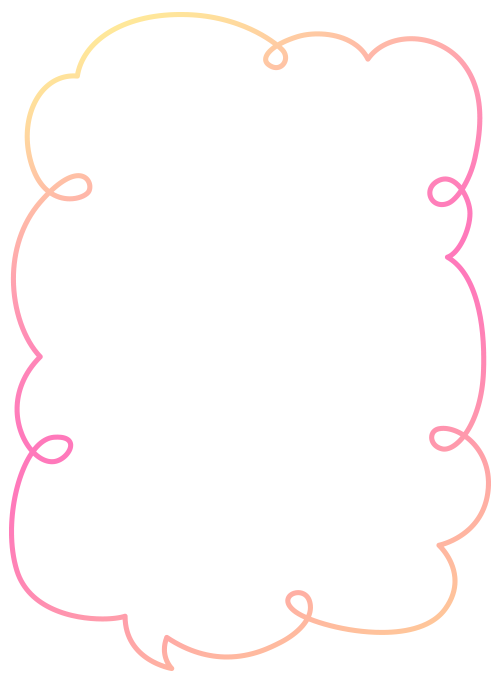隣の席になったことだけが理由じゃない。
あたしの中で、洸輝という存在は確実に大きくなっていっていたんだ。
日を追うごとに、その気持ちは風船のようにどんどんふくれあがる。
洸輝と同じ香水をつけている人とすれちがうと、自然と目で追ってしまったりもした。
洸輝の声がするだけでくすぐったい気持ちになったし、『花凛』と名前を呼ばれただけでドキドキした。
こんな気持ちになるなんて思わなかった。
最初から、洸輝と付き合えるとは思っていない。
そんな高望みはしていない。
ただ、もっとそばにいたかった。
隣の席でたわいない会話を交わすだけだっていい。
それだってあたしにとってこれ以上ない幸せだから。