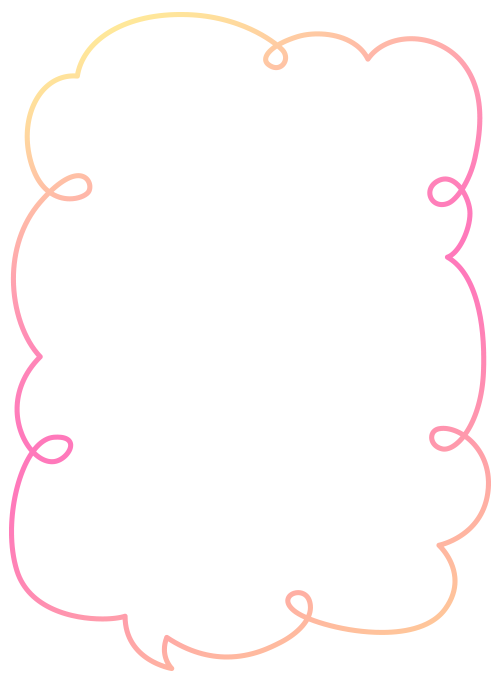「どうしたんだよ、急に」
困ったような驚いたような複雑そうな洸輝の顔。
「ごめんね……。やっぱりちょっと調子悪いから……。あたし、帰るね」
「わかった。それなら、家まで送る」
「……大丈夫だから」
「でも……」
「お願いだから、ひとりにして」
そう頼むと、洸輝はしぶしぶ聞き入れてくれた。
「わかった。気をつけて帰れよ?」
「うん……。ありがとう」
笑顔を浮かべようとしたけれど、うまく笑えていなかっただろう。
洸輝と林くんに背中を向けて歩きだしたと同時に、こらえていた感情が一気に涙となってあふれだす。
ふたりに気づかれないように、うつむくことなく正面を向いたまま涙を流した。
困ったような驚いたような複雑そうな洸輝の顔。
「ごめんね……。やっぱりちょっと調子悪いから……。あたし、帰るね」
「わかった。それなら、家まで送る」
「……大丈夫だから」
「でも……」
「お願いだから、ひとりにして」
そう頼むと、洸輝はしぶしぶ聞き入れてくれた。
「わかった。気をつけて帰れよ?」
「うん……。ありがとう」
笑顔を浮かべようとしたけれど、うまく笑えていなかっただろう。
洸輝と林くんに背中を向けて歩きだしたと同時に、こらえていた感情が一気に涙となってあふれだす。
ふたりに気づかれないように、うつむくことなく正面を向いたまま涙を流した。