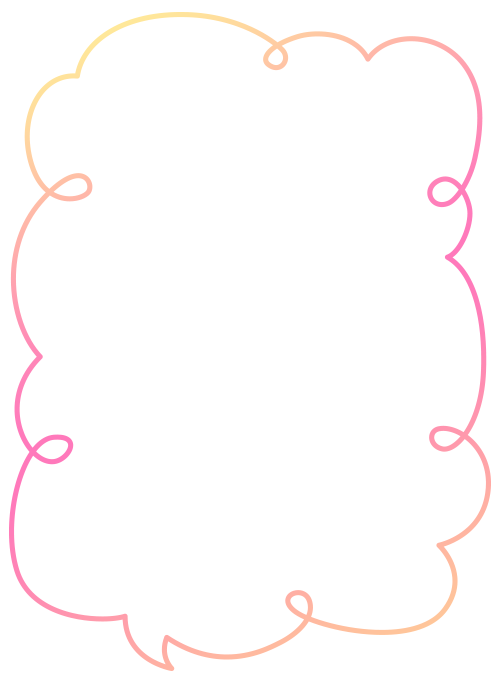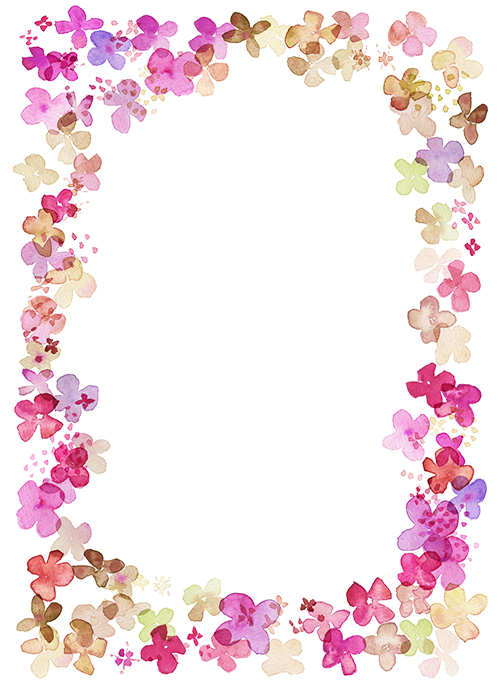「ごめんね。ぜんぜん気づかなかったよ」
「マジか。俺はすぐ花凛だって気づいたのに」
さっき泣きそうになっていたの、洸輝に見られていないよね……?
おそるおそる洸輝の顔色をうかがう。
「ん?」
「ううん、なんでもない」
よかった。やっぱり見られていなかったんだ……。
普段と変わらない様子の洸輝に、ほっと胸をなでおろす。
「ねぇ、洸輝はなんでここにいたの?」
「あぁ……べつに。たまたまヒマでブラブラしてただけ。花凛は?」
「あたしもそんな感じ……かな?」
なんとなくそうごまかすと、洸輝はニッと笑った。
「つーか、今ヒマなんだったら飯いこうぜ」
「ご飯?」
「そう。もう食った?」
「ううん、これからだけど……」
「じゃあ、決定。花凛なに食いたい? このあたりなんもないし、駅のほう行くか」
洸輝はさらっとそう言って歩きだす。
ご飯……って、ふたりで行くってことだよね?
休みの日に、洸輝とふたりっきりでいることすら信じられないっていうのに、一緒にご飯?
なんだかハードルが高い。
もし、洸輝と一緒にいるところを学校の女子に見られたら、大騒ぎになりそうだ。
「花凛? どうした?」
「あぁ、うん。ごめん、今いく!!」
ついてこないあたしに気づいて、振り返る洸輝。
あたしは小走りで洸輝の隣まで行くと、そろって歩きだした。
「マジか。俺はすぐ花凛だって気づいたのに」
さっき泣きそうになっていたの、洸輝に見られていないよね……?
おそるおそる洸輝の顔色をうかがう。
「ん?」
「ううん、なんでもない」
よかった。やっぱり見られていなかったんだ……。
普段と変わらない様子の洸輝に、ほっと胸をなでおろす。
「ねぇ、洸輝はなんでここにいたの?」
「あぁ……べつに。たまたまヒマでブラブラしてただけ。花凛は?」
「あたしもそんな感じ……かな?」
なんとなくそうごまかすと、洸輝はニッと笑った。
「つーか、今ヒマなんだったら飯いこうぜ」
「ご飯?」
「そう。もう食った?」
「ううん、これからだけど……」
「じゃあ、決定。花凛なに食いたい? このあたりなんもないし、駅のほう行くか」
洸輝はさらっとそう言って歩きだす。
ご飯……って、ふたりで行くってことだよね?
休みの日に、洸輝とふたりっきりでいることすら信じられないっていうのに、一緒にご飯?
なんだかハードルが高い。
もし、洸輝と一緒にいるところを学校の女子に見られたら、大騒ぎになりそうだ。
「花凛? どうした?」
「あぁ、うん。ごめん、今いく!!」
ついてこないあたしに気づいて、振り返る洸輝。
あたしは小走りで洸輝の隣まで行くと、そろって歩きだした。