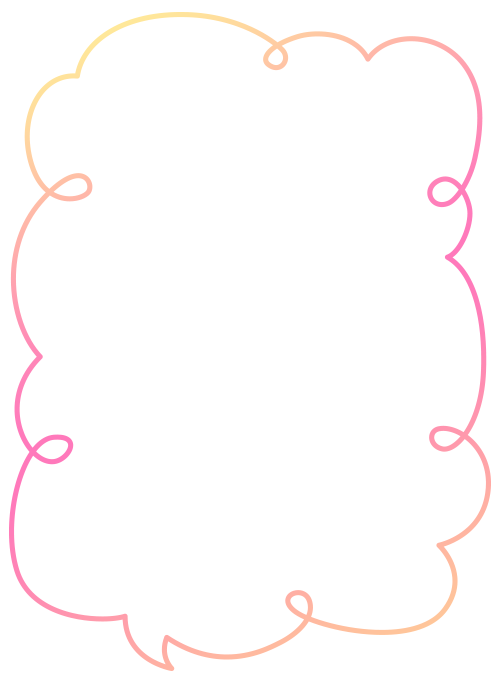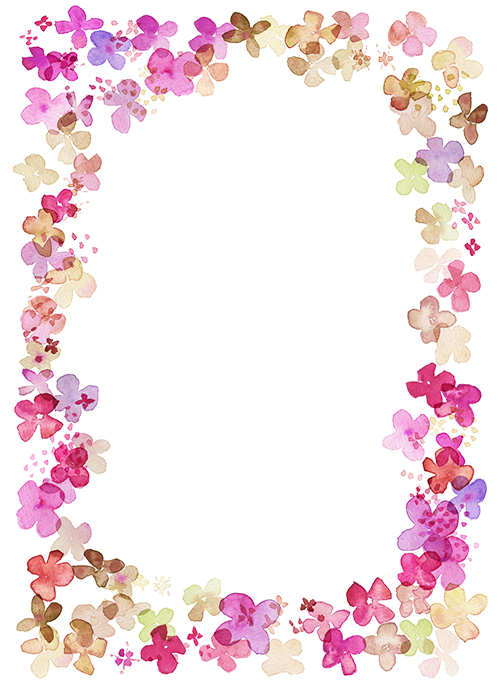「花凛、ごめんね。お母さん午後から仕事が入っちゃって……。ここに来る前にパート仲間の娘さんが熱を出しちゃったって連絡が来たの。だから――」
そっか。そういうことか。
「そっか。それなら仕方ないね。また今度にしよう?」
あたしはニコッと笑って答えた。
言いづらそうな母の代わりに、自分の気持ちをぐっとこらえる。
「でも、買い物に行きたかったんじゃないの?」
「いいの。急ぎじゃないから。あっ、仕事行くならここで別れたほうがいいよね? あたし、誰か友達誘って一緒にご飯食べるから気にしないで?」
「ごめんね、花凛。今度の週末は休みとるからね。そしたらどこか――」
「あっ、友達から電話来た!! じゃあ、お母さんまたねっ!!」
鳴ってもいないスマホを取り出して、母に背を向けて走りだす。
これでよかったんだ。
あたしが我慢すればみんながうまくいく。
母が見えなくなるところまで走り、立ち止まって呼吸を整える。
でも期待していた分、少しだけ悲しい。
急に目頭が熱くなる。
ぐっと唇を噛んで我慢しようとしたとき、突然手もとのスマホが震えた。
そっか。そういうことか。
「そっか。それなら仕方ないね。また今度にしよう?」
あたしはニコッと笑って答えた。
言いづらそうな母の代わりに、自分の気持ちをぐっとこらえる。
「でも、買い物に行きたかったんじゃないの?」
「いいの。急ぎじゃないから。あっ、仕事行くならここで別れたほうがいいよね? あたし、誰か友達誘って一緒にご飯食べるから気にしないで?」
「ごめんね、花凛。今度の週末は休みとるからね。そしたらどこか――」
「あっ、友達から電話来た!! じゃあ、お母さんまたねっ!!」
鳴ってもいないスマホを取り出して、母に背を向けて走りだす。
これでよかったんだ。
あたしが我慢すればみんながうまくいく。
母が見えなくなるところまで走り、立ち止まって呼吸を整える。
でも期待していた分、少しだけ悲しい。
急に目頭が熱くなる。
ぐっと唇を噛んで我慢しようとしたとき、突然手もとのスマホが震えた。