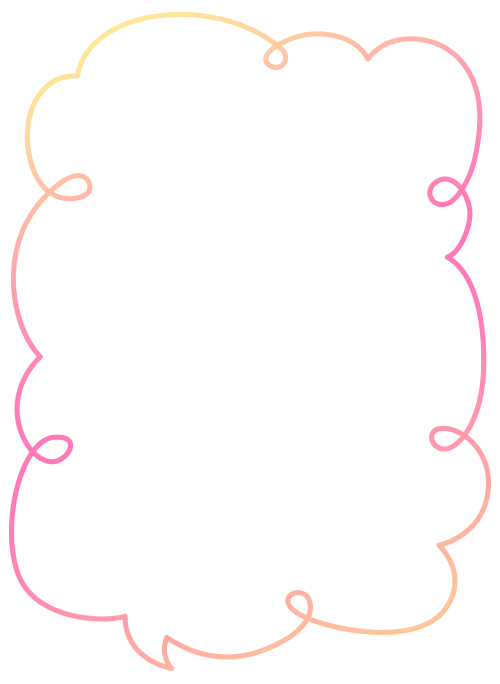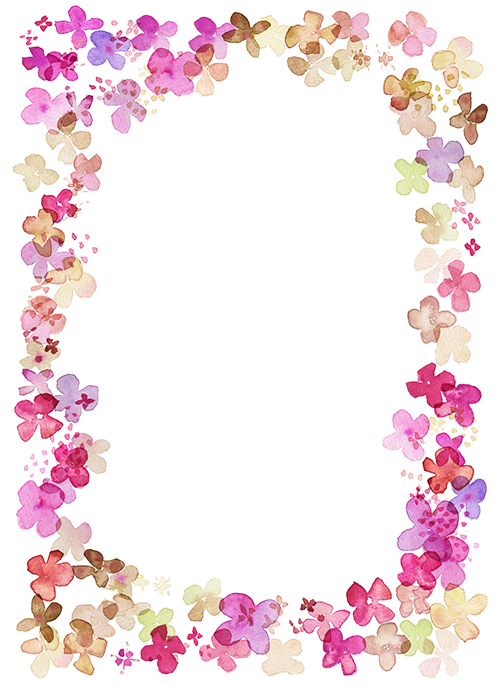「そうなのね。でも、いつかお母さんがお父さんに出会えたように、花凛にも大切な人ができたらいいわね」
母はそう言うと、ほんの少しだけさみしそうに目を伏せた。
母は6年経った今も、父を想っているんだろう。
父と母はあたしが知る限り、一度だってケンカをしたことがない。
幼い頃、友達にもよく『花凛ちゃんのお父さんとお母さんって仲よしだよね』と言われて、うれしかったことを今もよく覚えている。
「お父さんが亡くなってから……もう6年も経つんだね」
「そうね。今でもどこかにいそうな気がするし、『ただいま』って笑って帰ってくるような気がする。そんなことありえないってわかってるのにね」
「お母さん……」
「花凛にもさみしい思いをさせてごめんね」
「ううん、いいの。お母さんがあたしのためにがんばってくれてるの知ってるから」
本心だった。
母のがんばりは痛いぐらいにわかっている。
もう少し手を抜いてもいいのにとすら思う。
白髪が多くなり、少し痩せた母があたしは心配でたまらなかった。
「あら……」
父のお墓の前まで来て母が声を漏らす。
父の墓前に花がたむけられている。
線香の煙もまだ立ちのぼっている。
あたしたちより先に、誰かがお父さんのお墓参りに来ていたようだ。
「誰が来てくれたのかしら」
「誰だろうね……」
「もしかしたら、お父さんの会社の人かもしれないわね。ほら、お父さんの親友の……」
「――それはないよ」
母の言葉にあたしは顔を強張らせた。
病気になったとたん、会社は父を切り捨てた。
母はそう言うと、ほんの少しだけさみしそうに目を伏せた。
母は6年経った今も、父を想っているんだろう。
父と母はあたしが知る限り、一度だってケンカをしたことがない。
幼い頃、友達にもよく『花凛ちゃんのお父さんとお母さんって仲よしだよね』と言われて、うれしかったことを今もよく覚えている。
「お父さんが亡くなってから……もう6年も経つんだね」
「そうね。今でもどこかにいそうな気がするし、『ただいま』って笑って帰ってくるような気がする。そんなことありえないってわかってるのにね」
「お母さん……」
「花凛にもさみしい思いをさせてごめんね」
「ううん、いいの。お母さんがあたしのためにがんばってくれてるの知ってるから」
本心だった。
母のがんばりは痛いぐらいにわかっている。
もう少し手を抜いてもいいのにとすら思う。
白髪が多くなり、少し痩せた母があたしは心配でたまらなかった。
「あら……」
父のお墓の前まで来て母が声を漏らす。
父の墓前に花がたむけられている。
線香の煙もまだ立ちのぼっている。
あたしたちより先に、誰かがお父さんのお墓参りに来ていたようだ。
「誰が来てくれたのかしら」
「誰だろうね……」
「もしかしたら、お父さんの会社の人かもしれないわね。ほら、お父さんの親友の……」
「――それはないよ」
母の言葉にあたしは顔を強張らせた。
病気になったとたん、会社は父を切り捨てた。