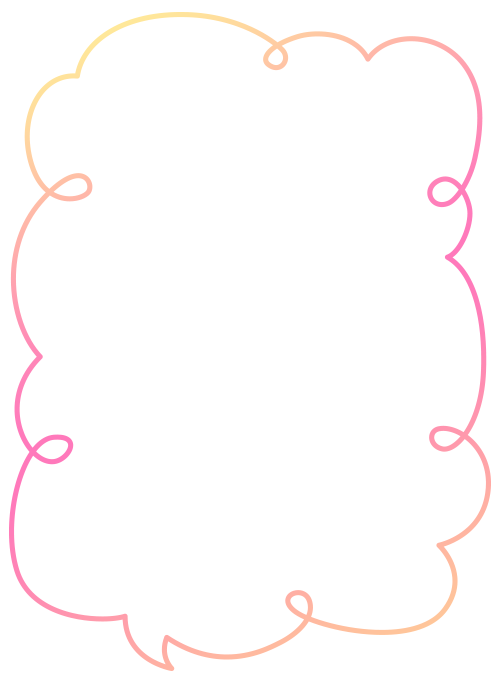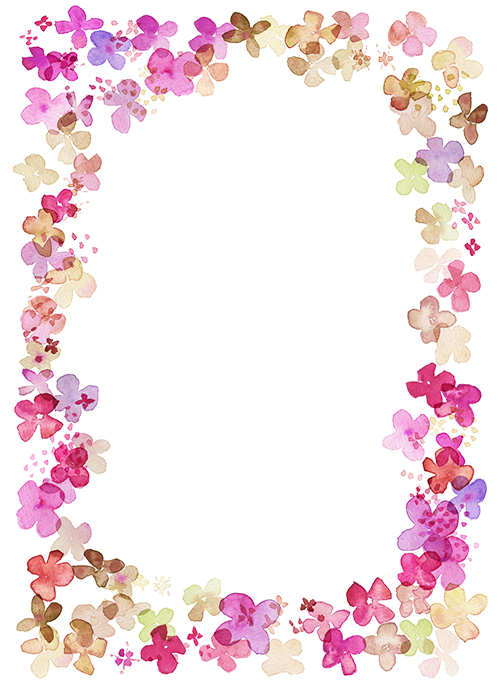「……っ……うぅ……」
お父さんのことで、人前で泣いたのは初めてだった。
今までどんなことがあっても泣かずにいられたのに、日向くんの前では涙腺が壊(こわ)れたかのように涙が止まらない。
そのとき、屋上に休み時間の終わりを告げるチャイムが鳴り響いた。
「ごめん……もう大丈夫だから」
涙をぬぐって日向くんから離れる。
その瞬間、日向くんの熱がスッと体から消えて急に心細くなった。
「なんか、いろいろごめんね……」
赤くなった目を見られたくなくて、うつむきながら日向くんの横を通りすぎようとした時、パシッと手首をつかまれた。
「名字で呼びあうのやめよう」
「……え?」
至近距離で目が合い、ドクンッと心臓が震える。
「俺のことは洸輝でいいから。俺も、花凛って呼びたいし」
向かいあうと急に照れくさくなって目をそらしてしまう。
「な、なんで……?」
不意に口をついて出てしまった言葉。
正直、どうして日向くんがあたしにいろいろなことをしてくれるのかわからなかった。
「特別だから」
日向くんはハッキリとした口調でそう言った。
お父さんのことで、人前で泣いたのは初めてだった。
今までどんなことがあっても泣かずにいられたのに、日向くんの前では涙腺が壊(こわ)れたかのように涙が止まらない。
そのとき、屋上に休み時間の終わりを告げるチャイムが鳴り響いた。
「ごめん……もう大丈夫だから」
涙をぬぐって日向くんから離れる。
その瞬間、日向くんの熱がスッと体から消えて急に心細くなった。
「なんか、いろいろごめんね……」
赤くなった目を見られたくなくて、うつむきながら日向くんの横を通りすぎようとした時、パシッと手首をつかまれた。
「名字で呼びあうのやめよう」
「……え?」
至近距離で目が合い、ドクンッと心臓が震える。
「俺のことは洸輝でいいから。俺も、花凛って呼びたいし」
向かいあうと急に照れくさくなって目をそらしてしまう。
「な、なんで……?」
不意に口をついて出てしまった言葉。
正直、どうして日向くんがあたしにいろいろなことをしてくれるのかわからなかった。
「特別だから」
日向くんはハッキリとした口調でそう言った。