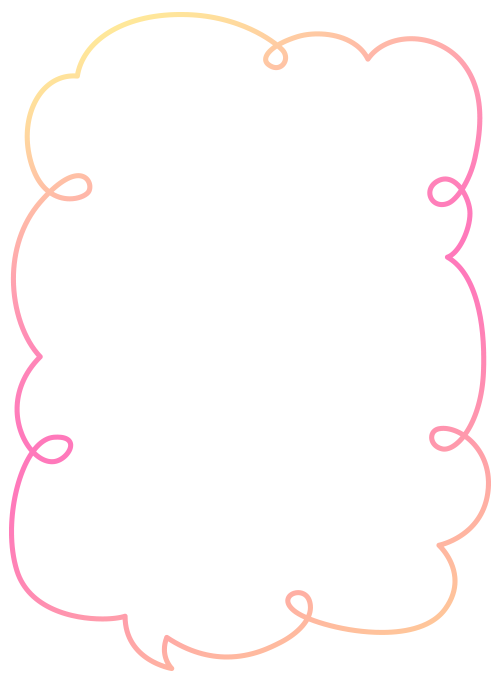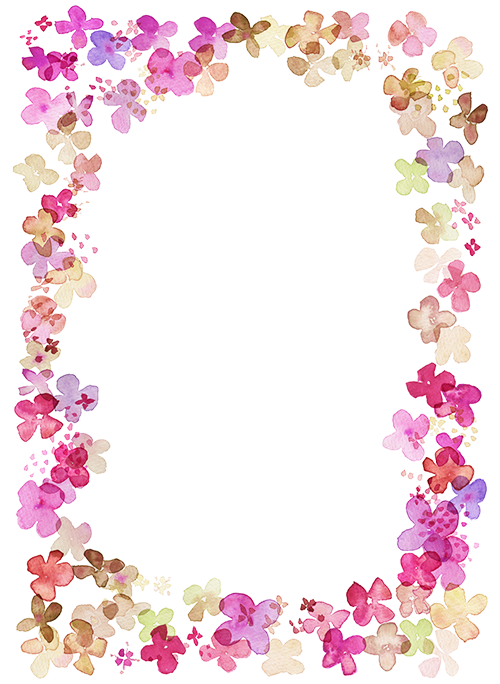『父さんは、この町が大好きなんだ。だから、この町をたくさんの人に知ってもらって、住むことで幸せだなって思ってくれる人がひとりでも増えたらうれしいんだ』
利益を優先することなく、人と人とのつながりを大切にしようとする、そんな父をあたしは誇りに思っていた。
父が病に倒れたのは、立ちあげた会社がようやく軌道に乗りはじめたという頃だった。
仕事人間だった父は、病気が発覚したあとも仕事を続けた。
『仕事はお父さんの生きがいだ』
そう言う父を誇らしく思っていた。
けれど、父の願いもむなしく、ある日父が肩を落として帰ってきた。
その日、父と母が夜遅くにリビングで話していたのをこっそり聞いてしまった。
『クビになったよ』
そう言って頭を抱える父を、母は必死に励ましていた。
あのとき、父は泣いていたのかもしれない。
丸くなった父の背中が少し小さく見えた。
今まで一度だって涙を流すことのなかった父が見せた、最初で最後の涙。
その日の記憶は5年以上経った今も色あせることなく、つらい記憶として胸に刻みこまれている。
利益を優先することなく、人と人とのつながりを大切にしようとする、そんな父をあたしは誇りに思っていた。
父が病に倒れたのは、立ちあげた会社がようやく軌道に乗りはじめたという頃だった。
仕事人間だった父は、病気が発覚したあとも仕事を続けた。
『仕事はお父さんの生きがいだ』
そう言う父を誇らしく思っていた。
けれど、父の願いもむなしく、ある日父が肩を落として帰ってきた。
その日、父と母が夜遅くにリビングで話していたのをこっそり聞いてしまった。
『クビになったよ』
そう言って頭を抱える父を、母は必死に励ましていた。
あのとき、父は泣いていたのかもしれない。
丸くなった父の背中が少し小さく見えた。
今まで一度だって涙を流すことのなかった父が見せた、最初で最後の涙。
その日の記憶は5年以上経った今も色あせることなく、つらい記憶として胸に刻みこまれている。