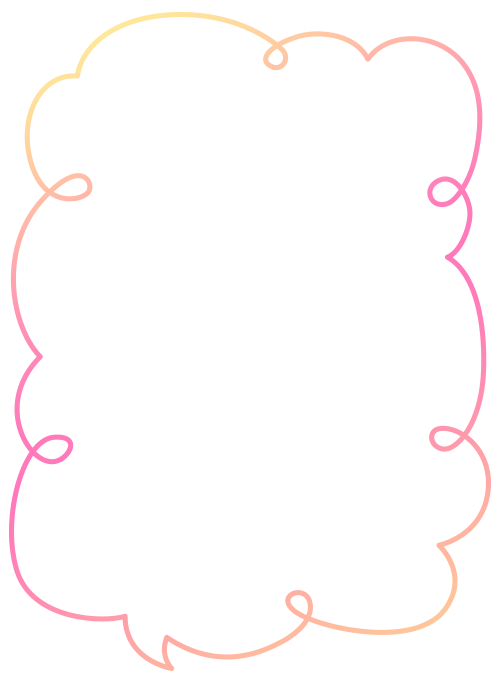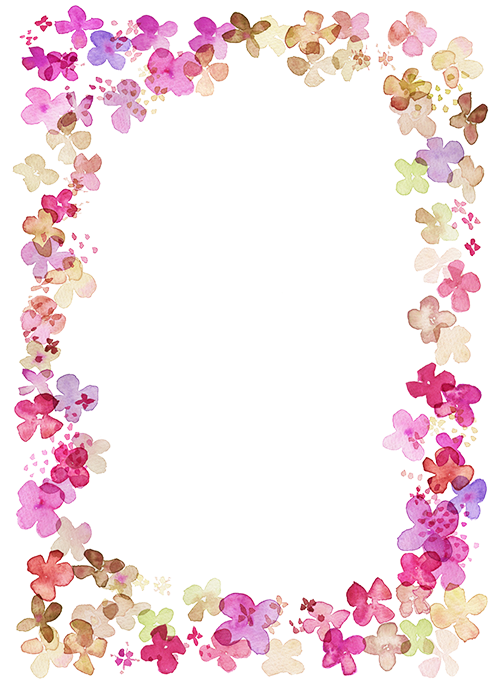「痛っ……!!」
休み時間になり、逢沢優亜の席にやってきたあたしは机を思いっきり蹴飛ばした。
机が腹部にぶつかったのか、顔を歪める逢沢。あたしは机の上の教科書やノートやペンケースを掴むと、そのまま窓際に歩み寄りそのまま下に放り投げた。
それだけではなくロッカーの中から取り出した体操着や体育館シューズをゴミ箱に投げ捨て、資料集を破いた。
クラスメイト達があたしの動向を目で追う。空気がひりついていく。
「アンタさ、最近調子に乗りすぎじゃない?」
再び逢沢優亜の席に戻ったとき、逢沢はゆっくりと顔を持ち上げた。
「調子に乗ってるのは沢木さん、あなたのほうでしょ?」
「は?」
逢沢優亜はスッと立ち上がると、あたしをまっすぐ見つめた。
「そういえば沢木さんって、昔から有名になりたかったんでしょ?ピアノを頑張っているのもそのため?」
「何言ってんだよ!!」
「あたしね、知ってるの。どうして沢木さんがそんなに頑張ってるのか。頑張って有名になれば、本当のお父さんが会いに来てくれるかもしれないって思ってるんでしょ?」
クイッと口の端を持ち上げた逢沢。どうして……どうしてそれをこの女が……?
「その反応、やっぱり図星みたいだね。沢木さんって実は純粋だったんだ?あなたを置いて家を出て行ったお父さんを今もけなげに思ってるなんてさ」
「どうして?どうしてアンタがそんなことを知ってるのよ!?」
Yシャツの襟元を掴んで叫ぶと、逢沢はにやりと笑った。
そして、口元を耳元に近付けると、そっとささやいた。
「早くお父さんと一緒に暮らせるようになるといいね?」
「アンタにあたしの何が分かるっていうの!?知ったような口きいてんじゃないわよ!!」
そう叫んで逢沢の頬を力いっぱい叩いた。
よろけた逢沢の髪をわしづかみにして腰に蹴りを入れる。
――何も知らないくせに。ふざけんな!!
逢沢の顔をもう一度殴ると、鮮血がポタポタと床に赤いシミを作る。
「キャー――!!」
「誰か先生呼んできて!!」
クラスメイト達の叫びが教室中にこだまする。
「……っ!!」
もう一発殴ってやろうかとしていたのに、逢沢の顔を見てゾッとした。
「あたしにこんなことをしたこと、絶対に後悔させてやる」
口の端から血を滴らせながら、逢沢は心底楽しそうに笑っていた。
休み時間になり、逢沢優亜の席にやってきたあたしは机を思いっきり蹴飛ばした。
机が腹部にぶつかったのか、顔を歪める逢沢。あたしは机の上の教科書やノートやペンケースを掴むと、そのまま窓際に歩み寄りそのまま下に放り投げた。
それだけではなくロッカーの中から取り出した体操着や体育館シューズをゴミ箱に投げ捨て、資料集を破いた。
クラスメイト達があたしの動向を目で追う。空気がひりついていく。
「アンタさ、最近調子に乗りすぎじゃない?」
再び逢沢優亜の席に戻ったとき、逢沢はゆっくりと顔を持ち上げた。
「調子に乗ってるのは沢木さん、あなたのほうでしょ?」
「は?」
逢沢優亜はスッと立ち上がると、あたしをまっすぐ見つめた。
「そういえば沢木さんって、昔から有名になりたかったんでしょ?ピアノを頑張っているのもそのため?」
「何言ってんだよ!!」
「あたしね、知ってるの。どうして沢木さんがそんなに頑張ってるのか。頑張って有名になれば、本当のお父さんが会いに来てくれるかもしれないって思ってるんでしょ?」
クイッと口の端を持ち上げた逢沢。どうして……どうしてそれをこの女が……?
「その反応、やっぱり図星みたいだね。沢木さんって実は純粋だったんだ?あなたを置いて家を出て行ったお父さんを今もけなげに思ってるなんてさ」
「どうして?どうしてアンタがそんなことを知ってるのよ!?」
Yシャツの襟元を掴んで叫ぶと、逢沢はにやりと笑った。
そして、口元を耳元に近付けると、そっとささやいた。
「早くお父さんと一緒に暮らせるようになるといいね?」
「アンタにあたしの何が分かるっていうの!?知ったような口きいてんじゃないわよ!!」
そう叫んで逢沢の頬を力いっぱい叩いた。
よろけた逢沢の髪をわしづかみにして腰に蹴りを入れる。
――何も知らないくせに。ふざけんな!!
逢沢の顔をもう一度殴ると、鮮血がポタポタと床に赤いシミを作る。
「キャー――!!」
「誰か先生呼んできて!!」
クラスメイト達の叫びが教室中にこだまする。
「……っ!!」
もう一発殴ってやろうかとしていたのに、逢沢の顔を見てゾッとした。
「あたしにこんなことをしたこと、絶対に後悔させてやる」
口の端から血を滴らせながら、逢沢は心底楽しそうに笑っていた。