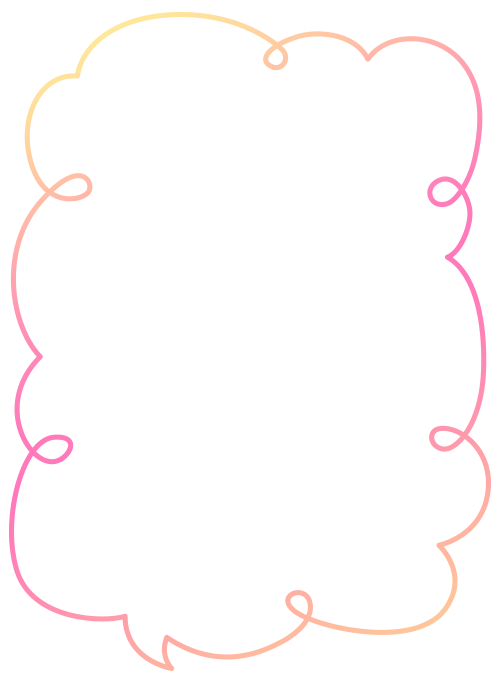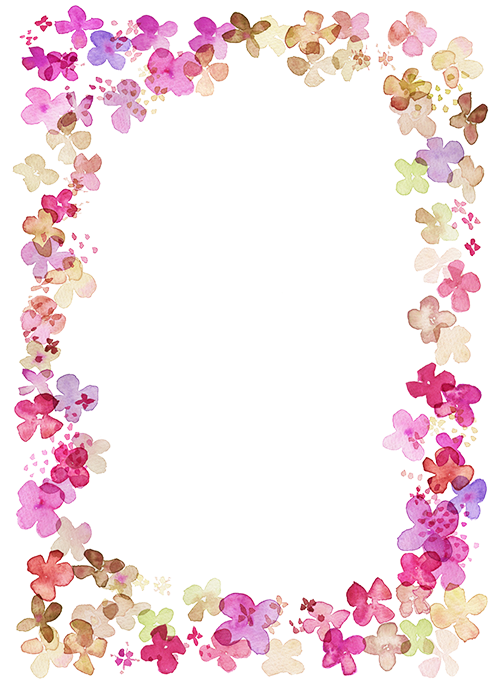「先生……」
絞りだした声はかすれていた。
「まだ何かあるの?」
呆れといら立ちの募った目を向け、腕を組む若菜先生。
「里ちゃんは……」
――元気にしていますか?
「あぁ、日野田さん?そういえばあなた友達だったわね。あの子はもう学校には来られないかもしれないわね」
「……えっ……」
里ちゃんがもう学校に来られない……?
「部屋から出られないそうよ。よくある不登校っていうやつね。仕方がないわ。高校は義務教育じゃないし、来られないなら来られないでほおっておくしかないでしょ」
「先生は……会いに行ってくれたんですか?里ちゃん……どんな様子だったんですか?」
「行くわけないでしょ。自分の意思で学校に来ない生徒の家を訪ねるほど暇じゃないわ」
バッサリと言い切った先生に目を見開く。
この人は……生徒のことなど何も考えていない。
すべて自分のことだけ。
「里ちゃんが急に学校に来なくなったのに、何かわけがあるとか考えないんですか?」
「わけがあるとしたら、それは自分のせいよ。クラスの中に自分の居場所を見つけられずに弾かれて不登校になるわけだから。学級委員なんてして目立とうとしたからじゃないかしら」
「――それは違います!!」
あたしが叫ぶと、先生はキッと鋭い目であたしを睨み付けた。