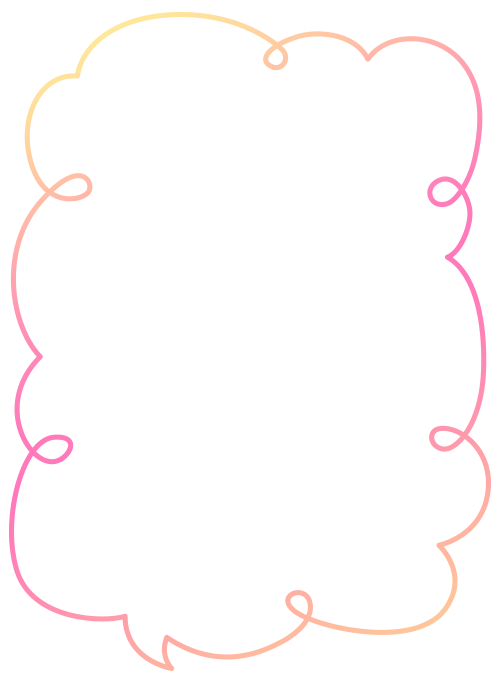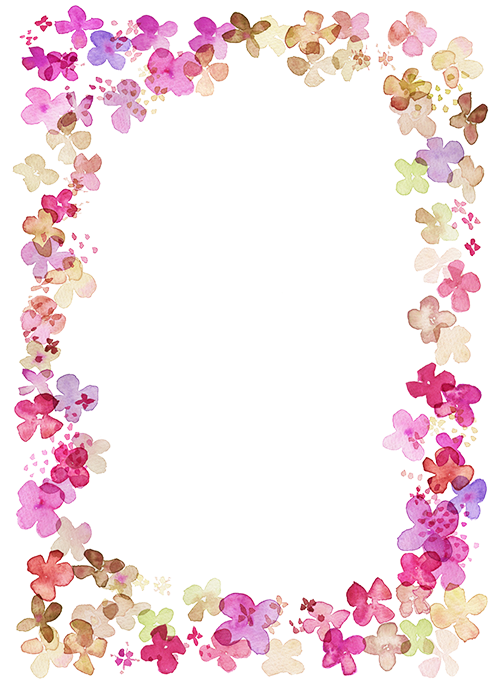グッと唇を噛みしめて叫び出してしまいそうなのを必死で押さえる。
それを見て何を勘違いしたのか、先生は優しく微笑んだ。
「言いたいことはそれだけよね?」
あたしの話など聞こうとはせず一方的に話を終わらせようとする先生。
でも、あたしが言いたいのはそれだけではなかった。
「柴村さんのことでも話があります」
「柴村さん?」
「はい。柴村さん、沢木さん達に飲み物を買いに行くように命令されているんです」
「命令?沢木さんたちが?」
「お金だって絶対に返していません。前にもそういうところをよく見かけました。それって立派なイジメですよね?」
イジメという言葉を出すと、先生の顔色がかわった。
「――疑ってかかるのはやめなさい。そもそもどうして柴村さんと沢木さんたちの問題にあなたが首を突っ込もうとするの?おかしいでしょ?」
「柴村さんとあたしは友達です。だから……」
「あのね、さっきから聞いてるとあなたの言っている言葉は信用ならないのよ。仮に沢木さん達が飲み物を買うように柴村さんに頼んだとして、それのどこがイジメになるっていうの?友達同士で飲み物を買ってきてと頼むのはイジメ?」
友達同士?綾香と柴村さんが……?どう考えたって違うにきまっている。