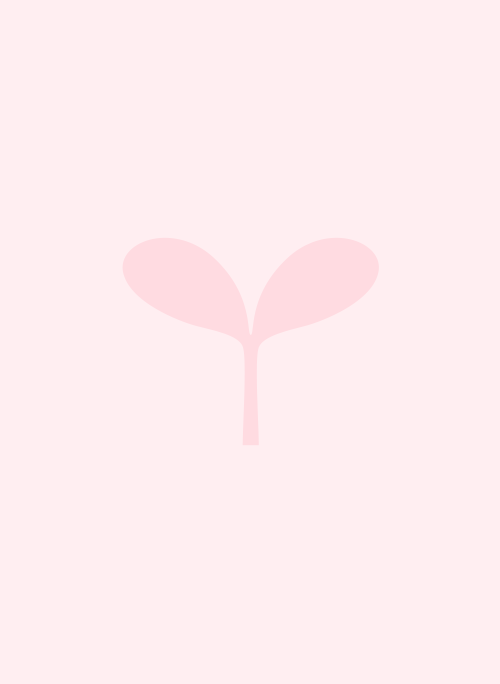え?と返したきり、僕は何も言えなくなった。
そんなこと考えたこともなかったし、僕はまだ誰かの葬式にも出たこともなかったから、人が死ぬということがどういうことなのか分からなかった。
「どうなるんだろう」
三角座りになった彼女はそう言って、両膝を抱えて顎を乗せた。
焼かれて、土になって、無くなるの。
親も、親戚も、クラスメートも先生も、最初は私のことを覚えていても、どんどん記憶が薄まって、顔も声も仕草もうろ覚えになって、それで、いつかは忘れるの。
それを悪いことだとは思わない。
それはすごく自然なこと。
そうやってきっとこれから私も生きていくの。
ゆっくりとかみ砕くように。
そう、彼女は僕に言った。
そんなこと考えたこともなかったし、僕はまだ誰かの葬式にも出たこともなかったから、人が死ぬということがどういうことなのか分からなかった。
「どうなるんだろう」
三角座りになった彼女はそう言って、両膝を抱えて顎を乗せた。
焼かれて、土になって、無くなるの。
親も、親戚も、クラスメートも先生も、最初は私のことを覚えていても、どんどん記憶が薄まって、顔も声も仕草もうろ覚えになって、それで、いつかは忘れるの。
それを悪いことだとは思わない。
それはすごく自然なこと。
そうやってきっとこれから私も生きていくの。
ゆっくりとかみ砕くように。
そう、彼女は僕に言った。