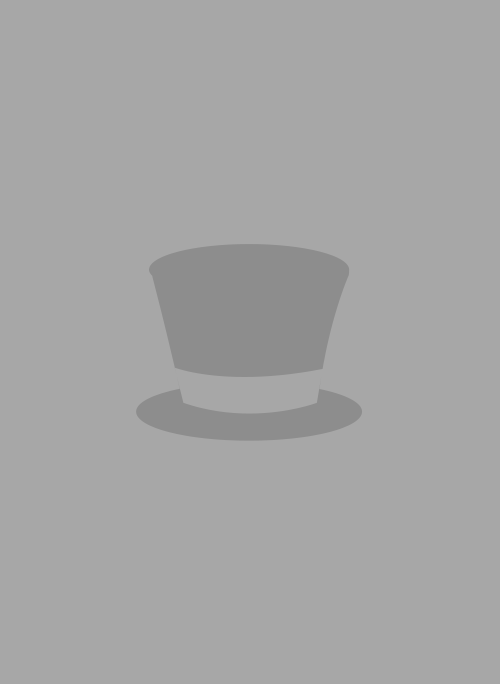英二はまだ乳飲み子の時に、児童施設の前に捨てられていた。
赤ん坊である英二が入ったカゴは、洗濯物を出し入れする時に使うようなプラスチックでできたカゴで、
バスタオル2、3枚に包まれていた。
その日は寒くなり始めた11月2日の夕方だった。
門の戸締りに来た施設長が泣いている英二に気付き、そっと抱きかかえ抱きしめた。
すぐさま病院で見てもらった赤ん坊は、雑に切られたへその緒が付いたままになっていて生後1日も経っておらず、
数時間遅ければ死んでいただろうと、医師は言った。
施設長はその赤ん坊に自分の名前の英一から一文字取って、英二と名付けた。
後に施設の職員からは、安易だと笑われたが、施設長は思ったより英二の名前に満足していた。
幼少期は何ら問題なく成長した英二だが、小学生になり暫くすると、周りからの声に心を閉ざし始めた。
自分がどういった人間なのかをわかってしまったのだ。
それは癒されることなく、心の傷は歳を重ねる毎に深くなり悪化していった。
いや正確に言えば施設長の愛で治っては、外で傷つくを繰り返し、瘡蓋の様なものになっていたのかもしれない。
その瘡蓋さえも作られなくなったのは高校二年になりたての春、施設長が亡くなった時だった。
英二はその頃から学校に行かなくなり施設にも帰らない日が増えた。
と、同時に隼とつるむようになった。
隼とは色んな事で気があった。
嫌な事も好きな事も、殆どが一緒だった。
のちに隼も施設育ちと知り、英二はだからか・・と納得が出来た。
だからなのか、全てが同じだと思いたかった。
全てを共有していたかった。
英二にとって、この世で自分を理解し認めてくれるのは、もう隼しかいないと思っていたからだ。
だから、どこかで違うと、間違っているのでは?と思いつつも英二は隼と共にいた。
やはり間違いだったんだと二年後に再度痛感することになるなんて思っていなかった。
赤ん坊である英二が入ったカゴは、洗濯物を出し入れする時に使うようなプラスチックでできたカゴで、
バスタオル2、3枚に包まれていた。
その日は寒くなり始めた11月2日の夕方だった。
門の戸締りに来た施設長が泣いている英二に気付き、そっと抱きかかえ抱きしめた。
すぐさま病院で見てもらった赤ん坊は、雑に切られたへその緒が付いたままになっていて生後1日も経っておらず、
数時間遅ければ死んでいただろうと、医師は言った。
施設長はその赤ん坊に自分の名前の英一から一文字取って、英二と名付けた。
後に施設の職員からは、安易だと笑われたが、施設長は思ったより英二の名前に満足していた。
幼少期は何ら問題なく成長した英二だが、小学生になり暫くすると、周りからの声に心を閉ざし始めた。
自分がどういった人間なのかをわかってしまったのだ。
それは癒されることなく、心の傷は歳を重ねる毎に深くなり悪化していった。
いや正確に言えば施設長の愛で治っては、外で傷つくを繰り返し、瘡蓋の様なものになっていたのかもしれない。
その瘡蓋さえも作られなくなったのは高校二年になりたての春、施設長が亡くなった時だった。
英二はその頃から学校に行かなくなり施設にも帰らない日が増えた。
と、同時に隼とつるむようになった。
隼とは色んな事で気があった。
嫌な事も好きな事も、殆どが一緒だった。
のちに隼も施設育ちと知り、英二はだからか・・と納得が出来た。
だからなのか、全てが同じだと思いたかった。
全てを共有していたかった。
英二にとって、この世で自分を理解し認めてくれるのは、もう隼しかいないと思っていたからだ。
だから、どこかで違うと、間違っているのでは?と思いつつも英二は隼と共にいた。
やはり間違いだったんだと二年後に再度痛感することになるなんて思っていなかった。