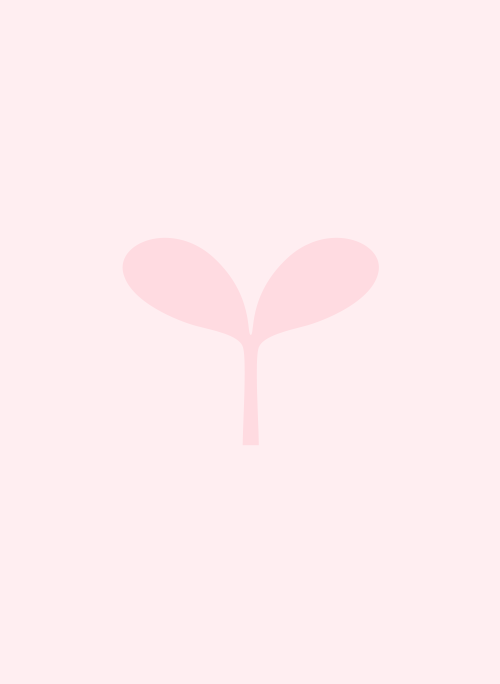「あのな、オハナ。俺、いろいろ考えてたんだよ。俺に何かできないかなって。だけど、俺が力を貸して、解決しても・・・・・・それは本当の意味での解決じゃない」
「マナ先輩、そんなこと考えてくれてたんですか」
「なんでだろうな。ここでオハナと会った日から、俺もちょっと変われたんだ。オハナが泣くのは俺も嫌だし、俺が泣くのはオハナも嫌なんだろうなって。わかんねぇけど、しっかり生きなきゃいけないなって思えた」
遠い目をしたマナ先輩の横顔は、キラキラと輝いていて、目が離せない。
「私もです!!私も、あの日から本当に変わった気がしてるんです。どこにいても、何をしててもマナ先輩が応援してくれてるような気がして」
「ははは。そこまで応援してねぇけどな。まぁ、お互いプラスな出会いだったってことか」
「はい!!」
穏やかな笑顔を浮かべたマナ先輩は、大きく息を吸って、真剣な顔をした。
「あのな、オハナ。テニス部の3年には知り合いも多いし、俺が一言言えば、嫌がらせはなくなるかもしれない。だけど・・・・・・それで、オハナは嬉しい?」
真剣になったマナ先輩の顔は、どこか切なくて、胸が苦しくなる。
こんなにも私のことを考えてくれていたなんて。
「自分の力で、解決しなきゃ、ですよね」
「そうだな。俺がかばうことで、表面上の嫌がらせがなくなっても、心の奥ではどうなるかわからない」
「そうですね。人気者の先輩にかばってもらえるなんて、余計に嫉妬されちゃうかもですね」
「その場合は、俺の親戚ってことにしようと思ってたんだけどな」
そこまで考えてくれて・・・・・・
泣いちゃうよ、私。