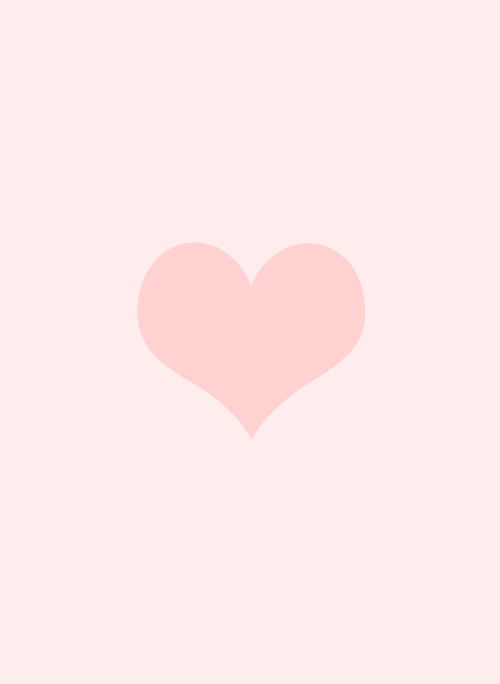高島は少しだけ私に近寄り、包み込むような言い方をした。
「話してしまえ。その方が楽になれる」
心理士でもないのにそう囁く。
その言葉に賭けるしか、今の自分が変われる道はない……と思った。
「……私は……生徒が男に見えて………女を………欲しがる狼のように思えて………怖くて…………怖くて………っ…」
ぎゅっと自分を抱いた。
「……うん……分かる。………怖かったんだな」
声を聞いた途端、声を殺して泣き伏せた。
誰も認めてくれなかった恐怖体験を、高島がやっと1人だけ認めてくれた。
「……うっ…ぐっ。…ひっずっ……ううっ…ううっ……ううううっ………!」
畳に伏せた格好で泣きじゃくった。
その間、高島はずっと側に居てくれた。
時々「よしよし」とか「よく言ったな」と励ましながら、一切触れることもなく声をかけ続けてくれた。
グス、グス……と涙が枯れ始めた頃、近くに置いてあったお茶の葉を入れ替えて差し出した。
「……飲めよ。落ち着く」
卒倒した時と同じ行動を取られた。
その茶器を恐る恐る受け取り、そっと唇を付ける。
「火傷すんなよ。ゆっくり飲め」
声かけに頷きながら、淹れたての熱いお茶を啜った。
唇は震えて上手く飲むことはできなかった。
熱いのも重なって、小さな器の中のお茶が無くなるまで、随分と時間がかかってしまった。
「話してしまえ。その方が楽になれる」
心理士でもないのにそう囁く。
その言葉に賭けるしか、今の自分が変われる道はない……と思った。
「……私は……生徒が男に見えて………女を………欲しがる狼のように思えて………怖くて…………怖くて………っ…」
ぎゅっと自分を抱いた。
「……うん……分かる。………怖かったんだな」
声を聞いた途端、声を殺して泣き伏せた。
誰も認めてくれなかった恐怖体験を、高島がやっと1人だけ認めてくれた。
「……うっ…ぐっ。…ひっずっ……ううっ…ううっ……ううううっ………!」
畳に伏せた格好で泣きじゃくった。
その間、高島はずっと側に居てくれた。
時々「よしよし」とか「よく言ったな」と励ましながら、一切触れることもなく声をかけ続けてくれた。
グス、グス……と涙が枯れ始めた頃、近くに置いてあったお茶の葉を入れ替えて差し出した。
「……飲めよ。落ち着く」
卒倒した時と同じ行動を取られた。
その茶器を恐る恐る受け取り、そっと唇を付ける。
「火傷すんなよ。ゆっくり飲め」
声かけに頷きながら、淹れたての熱いお茶を啜った。
唇は震えて上手く飲むことはできなかった。
熱いのも重なって、小さな器の中のお茶が無くなるまで、随分と時間がかかってしまった。