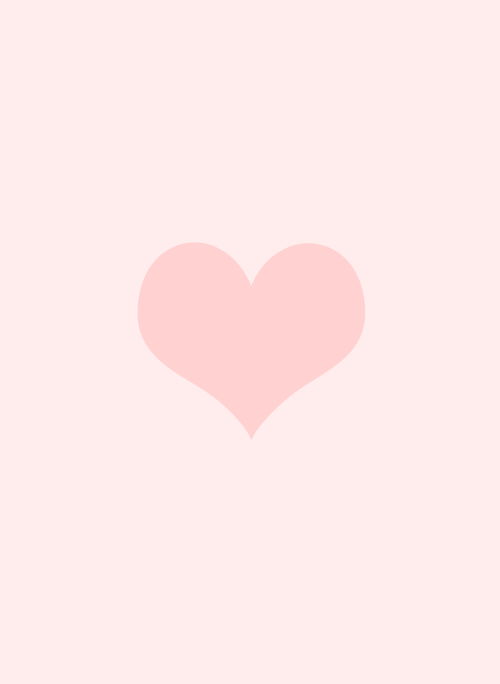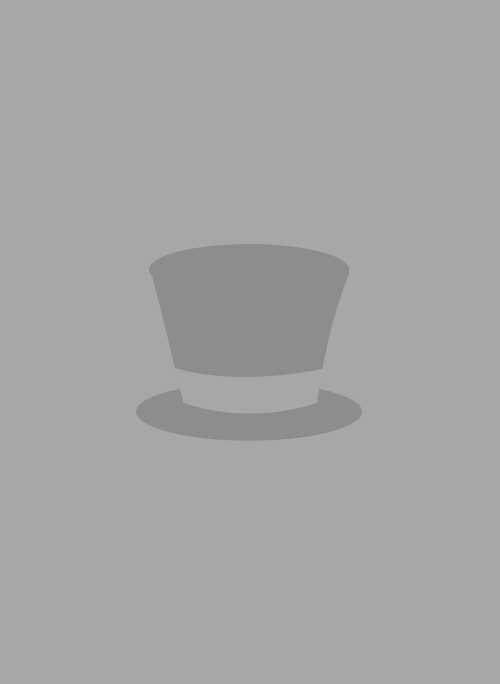「存在してしまった私は、消えなければなりませんでした」
彼女の話は、そんな言葉から始まった。そのタイミングは、まるで僕がこのベンチに座るのを待っているかのようだった。淡々と話すその様子は、やはり出会ったときや柊茉優とやりとりをしていたときと変わらない。見つめていれば吸い込まれそうなくらい真っ黒に澄んだ瞳は、もしかすると彼女の「生」をブラックホールのように飲み込んでいるのではないかと感じた。復讐をするという目的があるからこそ彼女は今ここで心臓を動かしているわけで、もしそれがなければ、彼女は生に執着することなく死へと向かっていったことだろう。
そういえばあのとき言葉を交わした彼女も、なんとなく、目の前にいる彼女と似た雰囲気を感じさせた。感情を失くしてしまった者は誰よりも強く生きられると思う、なんてことを言っておきながら、彼女の瞳はそんな風に生きることを考えていないように感じたのだ。むしろ、生きるというよりも死ぬことを見ているような眼をしていた。これは自惚れでも何でもなくて、もしかするとあのとき彼女が言ったあの言葉は、僕に対して向けられたものではないのだろうかと思う。
感情の有無なんてどうだってよかった。喜びも、怒りも、哀しみも、楽しさも、僕にとってはどうでもよかった。どんなにいじめを受けていようが、怒りを感じたり悔しさを感じたりすることは無駄なことのように思えていたのだ。あの頃僕の中にあったのは、生への執着だけだったのだと思う。だからこそ「死んでしまおう」と思うこともなかった。
僕が忍耐強かったとか精神を保っていられたとか、そういうことでは全くない。きっと、あのときの彼女が、僕の中から、いずれ死に繋がるであろう全ての感情を、あの言葉によって僕の中から振り払ってしまったのだ。
あのときの彼女が、僕をこうして生かしていると言っても過言ではない。そうすると僕はもしかすると、彼女から生を奪ってしまっているのかもしれない。彼女とはあの一度きりの時間しか共に過ごしていない。あのときの彼女は、もう既に死に到着してしまっているかもしれない。
「あなたは、全てを知っていると思っていました。いいえ、全てを知っているはずなんです」
彼女はそう言うが、その「あなたは知っている」という言葉が、どうにも素直に入ってこない。ここでもない、あそこでもない、と僕の中でぴたりと納まる場所を探しているような違和感があった。
「君の言葉と僕の記憶の間で、何かのピースが欠けているんだ。思い出せないでいる僕も悪いと思うけれど、もう少し詳しく話してくれれば、もしかすると思い出すこともあるかもしれない」
言葉足らずなのだ。僕自身に思い出させようとしているのはわかっているけれど、それでもまだ、彼女の言葉と僕の記憶を繋げるには情報が少なすぎる。
わかりました、と静かに言って、彼女はまた話し始めた。