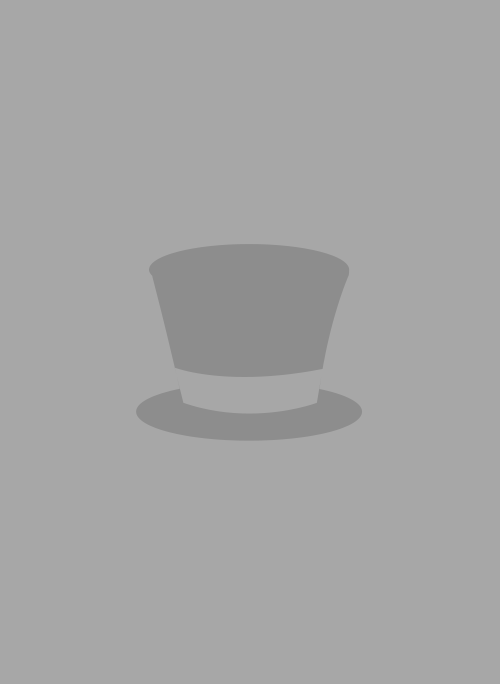2人の話を聞いている限りでは、確かに彼女は、僕と同じような時間を過ごしてきたのだと思う。考え方こそは違っているけれど、柊茉優の言う「人をばかにした眼」を、きっと僕もしていたはずだ。実際にばかにしていたのだから。
「私たちが2人揃っていることは、必然的なこと」
声を荒らげる柊茉優に対して、彼女の声は冷たく、そして落ち着いていた。
「私は存在していた。私という存在は、彼とともにあった。それが何かの手違いで、何かが原因で、彼と離れてしまったの」
僕はこの2人の会話を理解できないでいた。厳密に言えば、僕と同じ名前を持つ彼女の言っていることに対して、頭が追いついていなかった。
自分の存在は、彼とともにあった。
彼と離れてしまった。
彼女の言う彼とは、誰のことを指しているのだろう。彼と離れたという言葉の中には、一体どんな意味が含まれているのだろう。
「さよならをしましょう」話題を変えるように、彼女が言った。
「私が気に入らないのなら、私と永遠のさよならをしましょう。そうすれば、どこにいても私と会うことはない」
「意味がわからない。あなたたちがここに来なければいいだけの話でしょう」
反論する柊茉優。けれどもその意見は、僕も妥当だと思った。お互いに会わないようにするのなら、お互いの領域に足を踏み入れなければいいのだ。わざわざ顔を合わせてさよならをする必要なんてどこにもない。
「いいえ」けれども彼女はそれを否定した。
「私たちは、さよならをする必要がある」
言いながら、彼女は柊茉優との距離を少しずつ詰めていく。後ずさりする柊茉優。それでも彼女は、柊茉優が逃げた分だけ、いやそれ以上に前へ進んでいく。
くすんだ銀色のナイフが、彼女の手の中で光を放っている。ここで僕はようやく、彼女の言っていることやしようとしていることを理解できた。永遠のさよなら。そうか、そういうことだったのか。でも僕に彼女を止める権利はない。彼女がしようとしていることなのだ。しなければならない、と彼女が感じていることなのだ。それをどうして僕が止められると言うんだろう。
彼女が握りしめていたナイフは、雲の隙間から差し込む光を吸い込んで、どんよりと鈍く重く光っている。しかしそこには、まるで猛獣が獲物を狙うような鋭さも混ざっているようにも見えた。もしかするとその鋭さは、復讐に執着する彼女の瞳とリンクしているのかもしれない。
「さようなら」
振り下ろされる手に握られたナイフが、柊茉優の胸部へと噛みついた。滲み出る赤黒い血を気に留めることもなく、ナイフは柊茉優の皮膚を切り裂き、肉や心臓まで喰べ尽くそうと奥へ奥へと入っていく。黒いシミは服を汚していく。生命の中枢となる部分がダメージを負った瞬間を、僕は初めて見た。心臓の動きと連動するように服のシミはどんどん広がっていき、服が吸い取れなかった分は液体のまま足元へと落ちていく。黒かったはずの血は、光に照らされて真っ赤に見えた。こんな綺麗な赤を、僕は今までに見たことがない。
生命を維持できる最低限の量を下回ったのだろう、ナイフで刺さされた柊茉優の身体はぐらりと彼女の方へ傾いた。彼女は握る手にさらに力を入れ、ナイフごと柊茉優の身体を押した。すると柊茉優は、今度は後ろへと倒れていく。その力を利用して、彼女はナイフを抜いた。血がべっとりとついていたためか、軽く抜けた。
「行きましょう」
血の中で眠るように動かなくなった柊茉優を一瞥して、彼女は言った。その眼はもう、柊茉優を見ていない。
柊茉優と彼女は、もう会うことはない。柊茉優が人間の眼に怯える心配もない。もう何も、怖がらなくていい。
永遠のさよならをした瞬間だった。