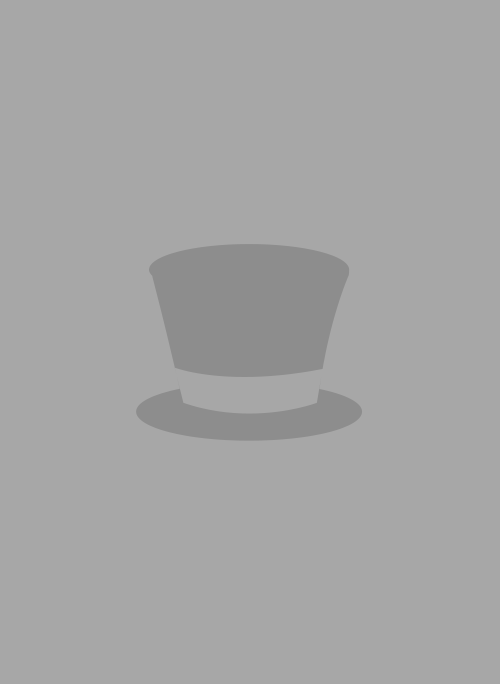駅を出て、そしてこの街に足を踏み入れて、30分以上は歩いただろうか。少しずつではあるけれど、家だけの風景の中に公園や空き地が現れ始めた。そこでは飼い犬の散歩をしている主婦や肩を並べて歩いている老夫婦が、静かな時間を過ごしている。夕方になれば学校帰りの子供たちが寄り道をして遊んでいそうな、そんな景色だった。
この街では昔から犯罪や不審者の情報が極めて少なかったが、その原因が今、ようやくわかった気がする。よそ者を入れまいとするように立ち並ぶ家々が、圧力を与えているのだ。だからこの街を出てよそ者となった僕にも、住んでいた頃とは全く違う雰囲気に感じられたのだ。どこか閉鎖しているようなこの街で、子供たちは守られているのである。
「ここです」
足を止め、彼女が言った。その目線の先には、落ち着いたブラウンの一軒家があった。柊と書かれた表札を見ると、確かにここは柊茉優の家で間違いないようだ。灰色のブロック塀で囲まれ、外からの情報や刺激をガードしているような印象だった。誰も来ないでくれ。堅いブロック塀から、そう訴えられている気がした。中学生の頃は自分と同じ思考や方針の者を仲間として受け入れていた柊茉優だったが、こうして家を隠すように囲む塀を見ると、本当にあの柊茉優の家なのかと思ってしまうほどだった。それほど、この家の様子は、柊茉優に似つかわしくなかった。
彼女がインターホンに手を伸ばした。ボタンに手が触れるか触れないかくらいのとき、その手を僕が遮った。
「僕が押すよ」
柊茉優への復讐は彼女の問題かもしれない。けれど同時にこれは、僕の問題でもあるのだ。柊茉優に恨みがあるわけではないけれど、でも、けじめとして、僕が顔を合わせるべきだと思った。
「ナイフ、私に持たせてくれませんか」
インターホンを押そうとした僕の手を、今度は彼女が遮った。自分の手で、というつもりなのだろう。彼女の瞳は、まっすぐ僕を見ていた。真っ黒なそれに、あのときと同じように吸い込まれそうだった。そしてそれは彼女の決意だった。
僕は鞄の中からナイフを取り出した。雲に邪魔をされながらもなんとか地上に届いている光を吸収したそれは、鈍く、そして濁った輝きを見せていた。
インターホンに再び手を伸ばす。指先にぐっと力を入れ、ボタンを押した。それと同時に、家の中にメロディが流れたのが外からでも聞こえた。
「どなたですか」母親らしき女性の声だった。
「柊茉優さんの中学生の頃のクラスメイトです」
嘘はつかなかった。友達の多かった柊茉優のことだ、名乗らなくても、クラスメイトだと言うだけで門を通してもらえると思ったのだ。そしてその予想は見事的中した。ガチャリという音とともに、門が抵抗なく開けられるようになった。
「どうぞ。茉優に出させますから玄関で待っていてください」
言われた通り僕らは門を通過し、玄関の扉には触ることなくそこで待つことにした。