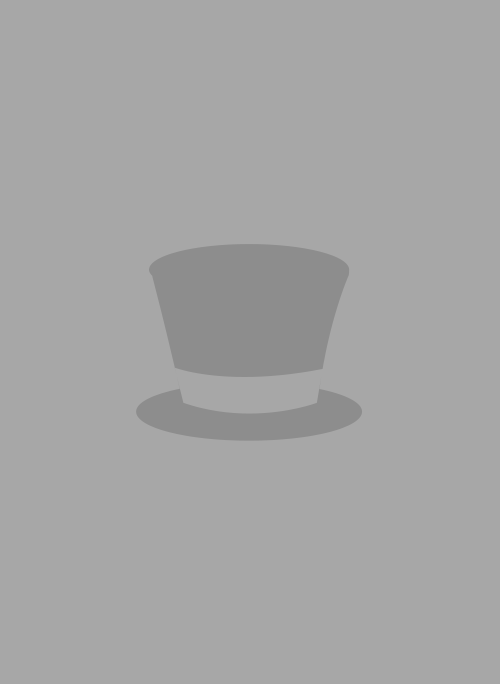「もう少しです」
彼女のその言葉に、僕ははっと我に返った。下を向いていたらしい顔を上げるも、目の前に見えるのはやはり何も変わらない家が並ぶだけの景色と、彼女のさらさらとしたショートヘアだけである。
「復讐を終えたら、君はどうするの?」
よくない意味で僕と関係のある2人に復讐をしたあと、彼女はどうするつもりなのだろう。そもそも、どうして彼女は柊茉優や岡崎拓海のことを知っているのだろう。中学生のとき、同じ教室に彼女なんていなかったはずなのだ。だけど、もしかすると、彼女と柊茉優たちは同じ小学校に行っていたのかもしれない。これは僕の勝手な憶測でしかないのだけれど、もし柊茉優や岡崎拓海にいじめ癖があったとして、彼女たちが同じ学校で出会っていたとして、そこで彼女を標的にしていたのだとしたら。僕のことを気に入らないといじめていたのだから、僕と似た要素を持つ彼女がいじめのターゲットにされてもおかしくはない。
けれど、そんな10年ほど前のことを根に持つだろうか。いじめは酷いものだったかもしれない。復讐をしたくなるほどのことをされたのかもしれない。でも、小学校や中学校で存在していた人間関係なんて、いずれは消えていくものだ。友達なんて、捨てていくものなのだ。
そんな昔関わっていたかもしれない人物に、そしてこれからきっと関わることなんてないであろう人物に復讐なんてして、それから彼女は一体どうするつもりなのだろう。
「さあ、どうするんでしょうね」
死ぬんじゃないですか、と彼女は言った。
それは、昨日の会話と繋がっているのだろうか。僕が彼女を殺す。そういう意味を含んでいるのだろうか。今の段階では、僕は彼女を殺すことはしないだろう。彼女が1人で死んでいくのだろうと思っている。
「そういうあなたは、どうするんですか」
「さあ、どうするんだろうね」
死ぬんじゃないかな、と僕は言った。未来のことは、誰にもわからない。一番いい方向に動いていけばいいけれど、その方向なんて誰にもわからない。だから僕たちは悩んで、迷って、苦しんで、足掻きながら生きていくんだ。未来からやってくる猫型ロボットなんて、僕たちの世界には存在しないのだから。
「あなたは、死にませんよ」
表情こそは見えないけれど、こちらに向けられたその声は、なんだか少し笑っているように聞こえた。冗談を言っているようにでも思えたのだろうか。それでもいい、と僕は思った。冗談だったなら彼女のように笑って流してしまえばいいし、もし本当に死ぬことになったなら、その瞬間まで彼女と一緒にいればいい。さようならと言いながら、一緒にこの世界から消えてしまっても、僕はきっと後悔しない。もしかするとどんな死に方よりも幸せかもしれない。
「あなたが死んでしまったら、私が生き続けないといけなくなっちゃうじゃないですか」
それだけは絶対に嫌です、と彼女はまた笑った。そんなに嫌なら君も一緒に死ねばいいじゃないか、と言うと、私が死んであなたが生きることに意味があるんです、とのこと。僕の人生に、彼女は一体何を見出しているのだろうか。大学にも行かず、アルバイトをするわけでもなく、ただただ無駄な時間を無駄に過ごしているだけのこの僕に、生きていて何の意味があるというのだろう。