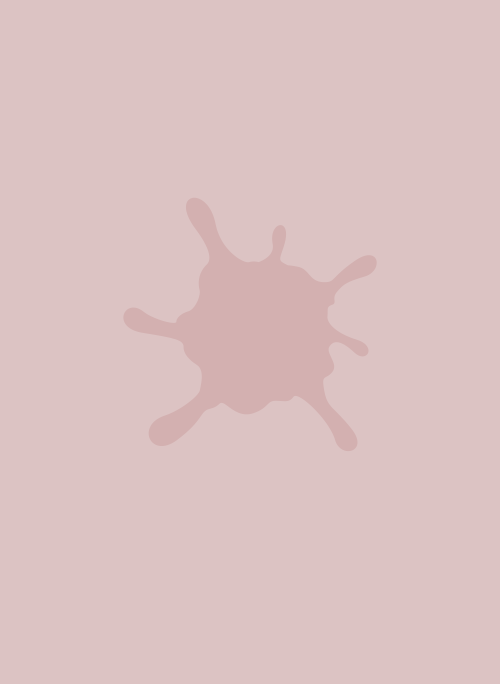わたしがどう反応していいか迷っている間にバスの扉が閉まった。そして、バスは車体を揺らすと走り出していた。
いつの間にか雨脚が強まり、街が霞んでいた。
あのままお店にいたら、この雨に巻き込まれ、もっと長時間お店にいる羽目になっただろう。
偶然とはいえ、まるで奇跡のような物事の流れに、思わず笑ってしまっていた。
「変な人」
わたしはそう言うと、唇を噛んだ。同時に彼に掴まれた手首が熱を持つのが分かった。その熱を紛らわせるために、もう一方の手で手首をつかんだ。
その熱がおさまってきたのを見計らい、傘を丁寧に畳んだ。彼に次に会ったときにはこれを返さないとけないから。連絡先どころか、名前も年齢も知らない。ただ、同じ高校に通っていた後輩に。
バスがわたしの家の近くの停留所に着くころ、亜津子たちからメールが届いた。
彼女のわたしの身を案じるメールに、勝手に帰って申し訳ないことと、知り合いに会ったことを伝えておいた。
いつの間にか雨脚が強まり、街が霞んでいた。
あのままお店にいたら、この雨に巻き込まれ、もっと長時間お店にいる羽目になっただろう。
偶然とはいえ、まるで奇跡のような物事の流れに、思わず笑ってしまっていた。
「変な人」
わたしはそう言うと、唇を噛んだ。同時に彼に掴まれた手首が熱を持つのが分かった。その熱を紛らわせるために、もう一方の手で手首をつかんだ。
その熱がおさまってきたのを見計らい、傘を丁寧に畳んだ。彼に次に会ったときにはこれを返さないとけないから。連絡先どころか、名前も年齢も知らない。ただ、同じ高校に通っていた後輩に。
バスがわたしの家の近くの停留所に着くころ、亜津子たちからメールが届いた。
彼女のわたしの身を案じるメールに、勝手に帰って申し訳ないことと、知り合いに会ったことを伝えておいた。