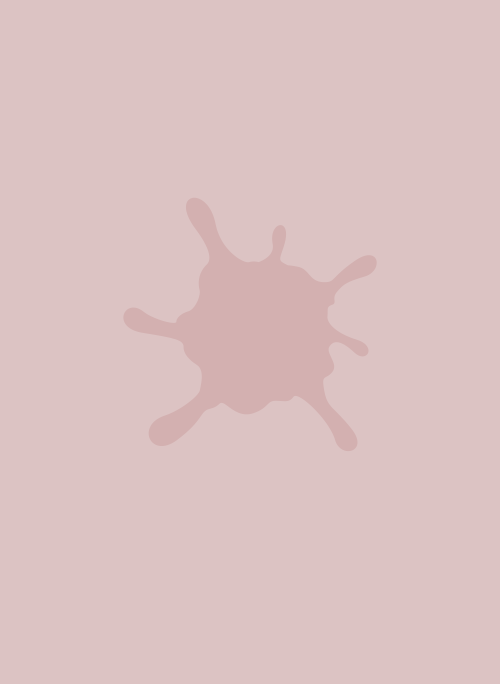この時期にしては強い、太陽の日差しを右手で遮ると、そのまま髪に触れた。そして、目の前にいる長身の男性に同意を求めた。
「どうかな? おかしくない?」
館川雄太はわたしを見て、優しく微笑んだ。
今日のために買った茶色のワンピースに、黒のパンプス。ストッキングやショルダーバッグまでも新調した。その姿は脳裏に思い描けるほどに家の鏡で繰り返し確認して、自己評価で満点をあげた。だが、目の前にいる最愛の人の同意が欲しかったのだ。
「おかしくないよ。それにきっと両親もほのかを気に入るよ。両親ともども楽しみにしているんだ」
「ありがとう」
わたしは優しい言葉に心を和ませた。今のわたしが一番ほしい言葉だ。
今日に限ったことではない。彼はいつもそうだ。わたしのほしい言葉をいつも口にしてくれた。
彼、館川雄太はとにかく優しい人だ。
わたしと彼が付き合い始めたのもそうだし、結婚を現実的な将来として思い描くようになったのも、彼の優しさによるところが大きい。
雄太はわたしの頭をそっと撫でた。
「それに緊張する必要もないと思うよ。両親は普通の人だし、きっと気に入ってくれると思う。ほのかは母さんには会ったことがあったよね?」
「うん。優しそうな人だね」
わたしは弾んだ口調で口にした。
「どうかな? おかしくない?」
館川雄太はわたしを見て、優しく微笑んだ。
今日のために買った茶色のワンピースに、黒のパンプス。ストッキングやショルダーバッグまでも新調した。その姿は脳裏に思い描けるほどに家の鏡で繰り返し確認して、自己評価で満点をあげた。だが、目の前にいる最愛の人の同意が欲しかったのだ。
「おかしくないよ。それにきっと両親もほのかを気に入るよ。両親ともども楽しみにしているんだ」
「ありがとう」
わたしは優しい言葉に心を和ませた。今のわたしが一番ほしい言葉だ。
今日に限ったことではない。彼はいつもそうだ。わたしのほしい言葉をいつも口にしてくれた。
彼、館川雄太はとにかく優しい人だ。
わたしと彼が付き合い始めたのもそうだし、結婚を現実的な将来として思い描くようになったのも、彼の優しさによるところが大きい。
雄太はわたしの頭をそっと撫でた。
「それに緊張する必要もないと思うよ。両親は普通の人だし、きっと気に入ってくれると思う。ほのかは母さんには会ったことがあったよね?」
「うん。優しそうな人だね」
わたしは弾んだ口調で口にした。