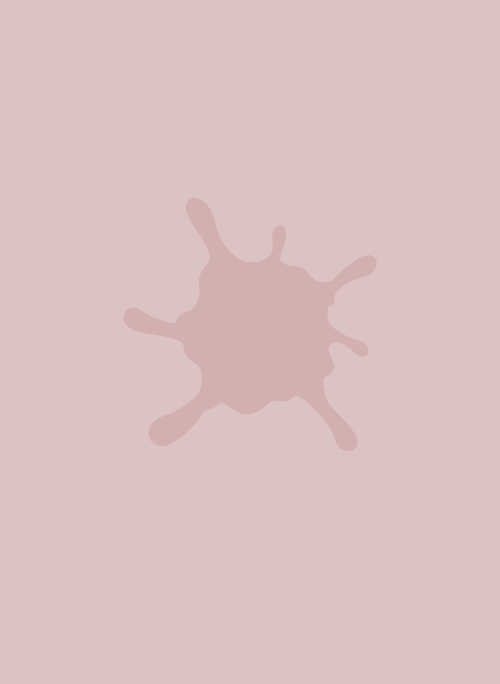わたしの分をおごっても、彼に何のメリットもないはずなのに。
わたしの足元に影が届き、顔をあげるときりんが首を伸ばして木に実っている葉を食べていた。
わたしの複雑な気持ちも一気に吹き飛んでいた。
「大きいね」
わたしの思わず漏らした言葉に、樹は微笑んだ。
「昔と同じこと言うんだな」
「そうだっけ?」
「そうだよ。幼稚園のときもそんなことを言っていた」
「よく覚えているね」
「記憶力はいいから」
樹は昔のような優しい笑顔で微笑んでいた。
その彼の表情を崩したくなかったため、入場料のことはしばらく封印しておくことに決めた。
彼は嫌々ついてきてくれたのかもしれないが、今日、彼とここに来て良かったと心から思っていた。
そのとき、数人の子供がぶつかり、わたしの傍を駆け抜けていく。
わたしは思わずその場でよろけた。
わたしの肩の部分に樹が触れ、体を支えてくれた。
「危ないな。大丈夫?」
「大丈夫」
「行くか」
彼はそういうと、歩き出す。
わたしはそんな樹の後を追った。
わたしの足元に影が届き、顔をあげるときりんが首を伸ばして木に実っている葉を食べていた。
わたしの複雑な気持ちも一気に吹き飛んでいた。
「大きいね」
わたしの思わず漏らした言葉に、樹は微笑んだ。
「昔と同じこと言うんだな」
「そうだっけ?」
「そうだよ。幼稚園のときもそんなことを言っていた」
「よく覚えているね」
「記憶力はいいから」
樹は昔のような優しい笑顔で微笑んでいた。
その彼の表情を崩したくなかったため、入場料のことはしばらく封印しておくことに決めた。
彼は嫌々ついてきてくれたのかもしれないが、今日、彼とここに来て良かったと心から思っていた。
そのとき、数人の子供がぶつかり、わたしの傍を駆け抜けていく。
わたしは思わずその場でよろけた。
わたしの肩の部分に樹が触れ、体を支えてくれた。
「危ないな。大丈夫?」
「大丈夫」
「行くか」
彼はそういうと、歩き出す。
わたしはそんな樹の後を追った。