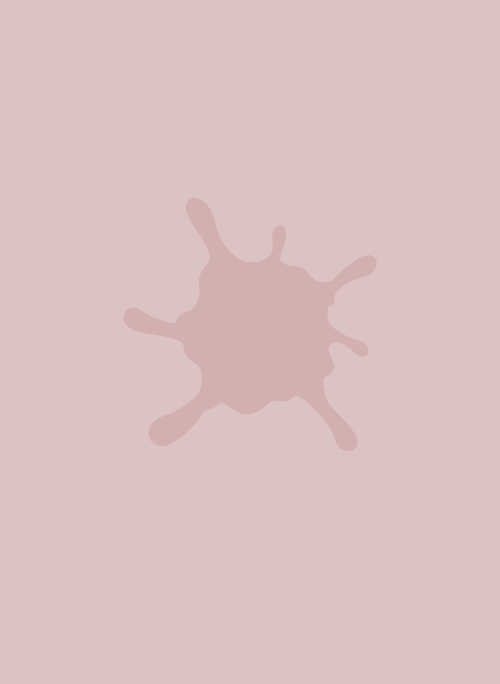これで少しは歩み寄れたのだろうか。
その答えはすぐには分からないが、樹の優しい表情がその答えのような気がした。
わたしはほっと胸をなでおろす。
これからもっとよい関係を樹と築いていけたらいい。
「でも、樹は悪戯っ子だよね。昨日も意味もなく、あんな嫌がらせをするんだもん」
いつの間にか真顔に戻った樹が呆れ顔でわたしを見る。
「お前、あれが嫌がらせだって思うわけ?」
「違うの?」
あんなことそうでなければしないはずだと思ったためだ。
樹は頭を抱える。
「何か面倒になってきた。嫌がらせでいいよ」
「違うなら、何?」
彼は冷たい目でわたしを見た。
「バカの相手をすると疲れる」
「樹に比べるとバカかもしれないけど、そんなにバカじゃないよ」
「どっちだよ」
「バカじゃない」
その時、樹の手が伸びてきて、わたしの頬に触れた。
心臓の跳ねを感じて樹を凝視する。
だが、次に襲ってきたのは頬の痛みだ。
彼はわたしから手を離す。
その答えはすぐには分からないが、樹の優しい表情がその答えのような気がした。
わたしはほっと胸をなでおろす。
これからもっとよい関係を樹と築いていけたらいい。
「でも、樹は悪戯っ子だよね。昨日も意味もなく、あんな嫌がらせをするんだもん」
いつの間にか真顔に戻った樹が呆れ顔でわたしを見る。
「お前、あれが嫌がらせだって思うわけ?」
「違うの?」
あんなことそうでなければしないはずだと思ったためだ。
樹は頭を抱える。
「何か面倒になってきた。嫌がらせでいいよ」
「違うなら、何?」
彼は冷たい目でわたしを見た。
「バカの相手をすると疲れる」
「樹に比べるとバカかもしれないけど、そんなにバカじゃないよ」
「どっちだよ」
「バカじゃない」
その時、樹の手が伸びてきて、わたしの頬に触れた。
心臓の跳ねを感じて樹を凝視する。
だが、次に襲ってきたのは頬の痛みだ。
彼はわたしから手を離す。